日本の牛乳はすべて国産。しかし、国産牛乳の背後にある現実をご存知ですか?
安全・安心な国産牛乳の供給を支えるため、実は飼料自給率の低さや輸入依存の課題と、経営を圧迫する飼料費の高さが大きな問題となっています。本記事では、現場で活躍する酪農家のリアルな声をもとに、その現状と将来的な課題、そして解決策に迫ります。

実は“国産牛乳”の裏には、海外からの飼料依存という落とし穴が…
1. 国産牛乳と乳製品自給率の違い
1.1 牛乳は100%国産の理由
- 品質管理の難しさ: 牛乳は温度管理や鮮度維持が非常に重要で、輸送中の品質低下を防ぐため、国内での生産が必須となっています。
- 安全・安心な供給体制: 短い流通経路と厳格な衛生管理の下で国産牛乳を提供することで、消費者の信頼を確保しています。

国産だからこそ、“新鮮”で“安全”なんだね!
1.2 乳製品自給率の実態
- 乳製品全体の自給率: 農林水産省の令和3年度データでは、牛乳・乳製品の品目別自給率は約65%にとどまっています。
→ 加工・保存が容易なチーズや脱脂粉乳などは、輸入に依存する部分が大きいためです。

加工や保存がしやすい製品は、どうしても海外からの供給に頼る部分が多いんです。
2. 飼料自給率が示す、酪農業の根本的な課題
2.1 現状の飼料自給率
農林水産省の令和4年度データによれば、乳牛に与える飼料は大きく次の2タイプに分けられます。
| 飼料タイプ | 自給率 |
|---|---|
| 粗飼料(例:チモシー、牧草) | 78% |
| 濃厚飼料(例:とうもろこし、トウモロコシ) | 13% |
| 全体 | 26% |
※飼料全体としてはわずか26%の自給率にとどまり、特に濃厚飼料の低さが際立っています。

濃厚飼料の輸入依存度が高いため、飼料費の高騰が酪農経営を圧迫しているんだね
2.2 飼料費が酪農経営に与える影響
現場で働く酪農家の声によると、**飼料費は経営コストの3~5割、場合によっては50~60%**を占めるため、特に円安の影響で輸入飼料の価格が上昇すると経営が非常に厳しくなります。
- 為替の影響: 円安によって輸入飼料のコストが急上昇し、経営圧迫が顕在化しています。
- コスト管理の重要性: 経営者は常に飼料費の変動に敏感で、国産飼料の生産拡大や自家配合への取り組みが求められています。

円安の影響で輸入飼料が高騰して、経営が厳しくなっているんですね
3. 日本の酪農業を取り巻く構造的課題
3.1 飼料自給率が低い理由
日本の飼料自給率が低い背景には、以下のような要因があります。
- 土地利用の限界: 国土の約70%が山地であり、広大な農地が限られているため、輸入飼料に頼るしかない現状があります。
- 栽培面積の減少: 飼料作物を栽培してきた農家が減少し、他の作物への転作が進むことで、生産面積が縮小しています。
- コスト面の競争: 国内生産の飼料は輸入飼料に比べて生産コストが高く、輸送や物流の点でも大規模海外生産の価格優位性に押される状況です。

土地が限られているから、輸入飼料に頼らざるを得ないんですね。
3.2 持続可能な酪農のために必要な取り組み
国産牛乳の品質を守るためには、単に牛乳生産だけでなく、飼料の自給率向上が必須となります。具体的には:
- 農地利用の効率化: 既存農地の効率的な利用と、テクノロジーを活用した作物管理の推進。
- 国産飼料の普及: 自家配合や地元産飼料の研究・普及、さらに政府の補助制度や支援策の拡充が必要です。
- サプライチェーンの再構築: 輸入依存から脱却するため、国内外の供給網の多角化・強化に努める取り組みが求められています。

輸入依存から脱却して、国内外の供給網を強化しないといけないね
4. 未来への展望:持続可能な酪農業の実現へ
酪農家として、また現場で活躍するプロの視点からは、今後の持続可能な酪農業実現に向けた取り組みが鍵となります。
現場からは、次のような声が寄せられています。
「円安が続くと飼料費の高騰は必然。経営コストの大きな割合を占める飼料費の負担が、日々の経営にダイレクトに響いています。国産飼料の生産・利用を広げ、輸入リスクを減らすことが急務です。」
この声は、業界全体が直面する課題を如実に物語っており、同時に食料安全保障の観点からも見逃せない問題といえます。

円安が続けば、飼料費が上がるのは避けられないよね。
5. まとめ
- 牛乳は100%国産: 鮮度と安全性が最優先され、国内生産される仕組みが確立。
- 乳製品自給率は65%: 輸入品の比重が高く、加工品では国産率が低下。
- 飼料自給率は26%: 特に濃厚飼料は13%にとどまり、輸入依存が深刻。
- 飼料費の影響: 為替変動で経営コストの3~5割から最大50~60%を占め、現場で大きな負担となっている。
持続可能な酪農業の実現のためには、国産飼料の普及と効率化、そして補助制度などを活用した国内生産の強化が求められています。牛乳を飲むたびに、未来の酪農業を支える一端が感じられるかもしれません。

国産牛乳の供給は安全で安心ですが、飼料自給率や乳製品の自給率には大きなギャップが存在するんだね


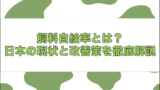

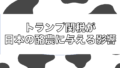
コメント