2025年7月、農林水産省(MAFF)が設置した「牛乳WG(ワーキンググループ)」では、牛乳の価格形成を透明化し、公正な取引を実現するための「コスト指標」作成が本格的に動き出しました。本記事では、その目的から調査手法、具体的な指標構成、活用シーン、そして今後の展望までをわかりやすくまとめています。

2025年、牛乳の価格がどう決まるか、ようやく“見える化”される時代に!
1. 牛乳WGの設立背景と目的
近年、牛乳をはじめとする乳製品価格は消費者の購入意欲に大きく影響し、酪農家・乳業メーカーの経営安定にも直結しています。
- 供給過剰と価格変動:原料乳の生産過多や輸入乳製品との競合により、卸売・小売価格が上下しやすい状況。
- 消費者の「牛乳離れ」:値上げやスーパーでの特売の頻度低下が影響し、年間消費量は漸減傾向。
- 酪農家の経営リスク:原料乳価格の急激な変動は、生産コストを賄いきれない赤字リスクを高める。
これらの課題に対応するため、牛乳WGは「生産から小売までの各段階におけるコストを可視化する指標」を作成し、価格交渉や改定時のベンチマークとして活用できる仕組みづくりを進めています。

酪農の“コストと価格のギャップ”に国が動き出したってことか
2. 調査対象とデータ収集の方法
WGでは、公的統計と独自アンケートを組み合わせ、以下3つのステージでコストを把握します。
- 生産段階(原料乳生産コスト)
- 飼料費、労働費、施設減価償却費など
- 基礎となる統計:畜産物生産費統計(令和3年度版)
- 対象:50~100頭規模の平均的な酪農経営
- 製造段階(乳業メーカーの製造コスト)
- 原料生乳費、包装材料費、労務費、燃料費など
- 既存の乳製品統計をベースに、大手メーカー数社へのヒアリング調査を実施
- 流通・販売段階(小売業者の販管費)
- 物流費、広告宣伝費、店舗運営費など
- 総務省「小売物価統計調査」やスーパーマーケット協会データを活用
各段階とも、最新データへのタイムラグ(公的統計は最大2年遅れ)が課題となるため、アンケート結果との組み合わせで補完を図っています。

牛乳1本の裏に“生産・製造・販売”それぞれのコストがある!
3. コスト指標の構成イメージ
WGで検討されている指標構成の骨組みは以下のとおりです。
| 段階 | 主なコスト項目 | 指標例 |
|---|---|---|
| 生産 | 飼料費、労務費、固定費(減価償却など) | 1頭当たり生産費:88万3,991円(令和3年度) |
| 製造 | 原料乳費、包装材費、労務費、燃料費 | 100kg当たり製造コスト:5,200円程度(概算) |
| 流通・販売 | 運送費、店舗運営費、広告宣伝費 | 1リットル当たり流通コスト:70円前後 |
指標は都道府県別にも算出し、地域差を反映。例えば北海道の広大な牧場経営と、都市部近郊の小規模経営ではコスト構造が異なるため、複数バージョンを用意する案も出ています。

北海道と都市近郊じゃ、コストの内訳が全然違うって納得
4. 活用シーンと期待される効果
- 価格改定のベンチマーク
コスト指標をもとに、自動改定方式や再交渉方式を導入することで、原料乳価格や市販価格の改定プロセスを効率化。 - 取引の透明性向上
生産者、メーカー、小売業者、さらには消費者に至るまで、各段階のコスト構造を理解できるようにし、納得性の高い価格形成を実現。 - 政策評価・改善
農林水産省(MAFF)や業界団体が、実際のコスト動向を把握。課題があれば補助金制度や支援プログラムの見直し材料に。 - 消費者の理解促進
「なぜ牛乳価格が上がったのか?」をグラフや解説で示すことで、消費者の信頼を醸成。将来的にはQRコード付きパッケージなどで情報提供も検討。

メーカーも小売も酪農家も“対等な関係”になってほしい…!
5. 課題と対応策
- 統計データの古さ:最新のコストを迅速に反映させるため、アンケートの定期実施頻度を年2回以上に拡大する提案あり。
- 地域差の多様性:複数モデルの指標を用意し、牧場規模や地形条件によるコスト差をカバー。
- 機密性の確保:企業ごとのデータではなく、複数社の平均値で公表。判断しやすい範囲で詳細内訳の開示を検討。
これらの対応策をWG内で詰め、「誰もが使いやすい指標」の実現を目指します。

“全国一律”ではなく、“現場目線の指標”が求められてる
6. 関連施策との連動
- 「牛乳でスマイルプロジェクト」
牛乳消費拡大と健康促進を掲げ、コスト指標と併せて消費者向けキャンペーンを展開。 - e-Stat「牛乳乳製品統計調査」
月次・年度別の生産量・在庫量データを指標の補完データとして活用。 - 食品システム法
2025年6月成立の新法に沿った透明性確保ルールとして、指標作成プロセスが位置づけられています。

牛乳でスマイルプロジェクトって、ちゃんと経済施策と連動してたんだ
7. 今後の展望
- 2026年4月施行の食品システム法に合わせ、早期に指標案を取りまとめ・公表
- 年1回更新を原則としつつ、物価上昇や異常気象時には臨時改定を実施
- 他品目(米、野菜、豆腐、納豆)への指標拡大にも技術的ノウハウを提供予定
これにより、日本の食料価格形成の透明性は飛躍的に向上し、消費者・生産者双方の安心感を高めることが期待されます。

牛乳の価格指標、2026年から“法律に基づく”仕組みに!
まとめ
- 牛乳WGの狙い:生産~流通~販売までのコスト見える化で価格交渉を公平化
- 指標構成:飼料費・労務費など生産コスト、包装材・労務費など製造コスト、物流費・店舗運営費など流通コストを網羅
- 活用方法:自動改定・再交渉方式の導入で価格改定プロセスを効率化
- 期待効果:消費者理解の促進、政策評価の高度化、酪農家の経営安定化
- 今後の展望:2026年4月の食品システム法施行に合わせた公表と、他品目への指標展開の可能性
牛乳WGが推進するコスト指標作成は、生産から小売までのコスト構造を“一目でわかる”形にし、公正な価格交渉と消費者理解を支援する画期的な取り組みです。統計データと独自調査を組み合わせ、地域差や経営規模の違いも反映。今後は制度設計の詰めを急ぎ、2026年の法施行に合わせて指標を公表する見通しです。

“なぜ牛乳が値上げ?”その答えが“数字で”わかるように!
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。


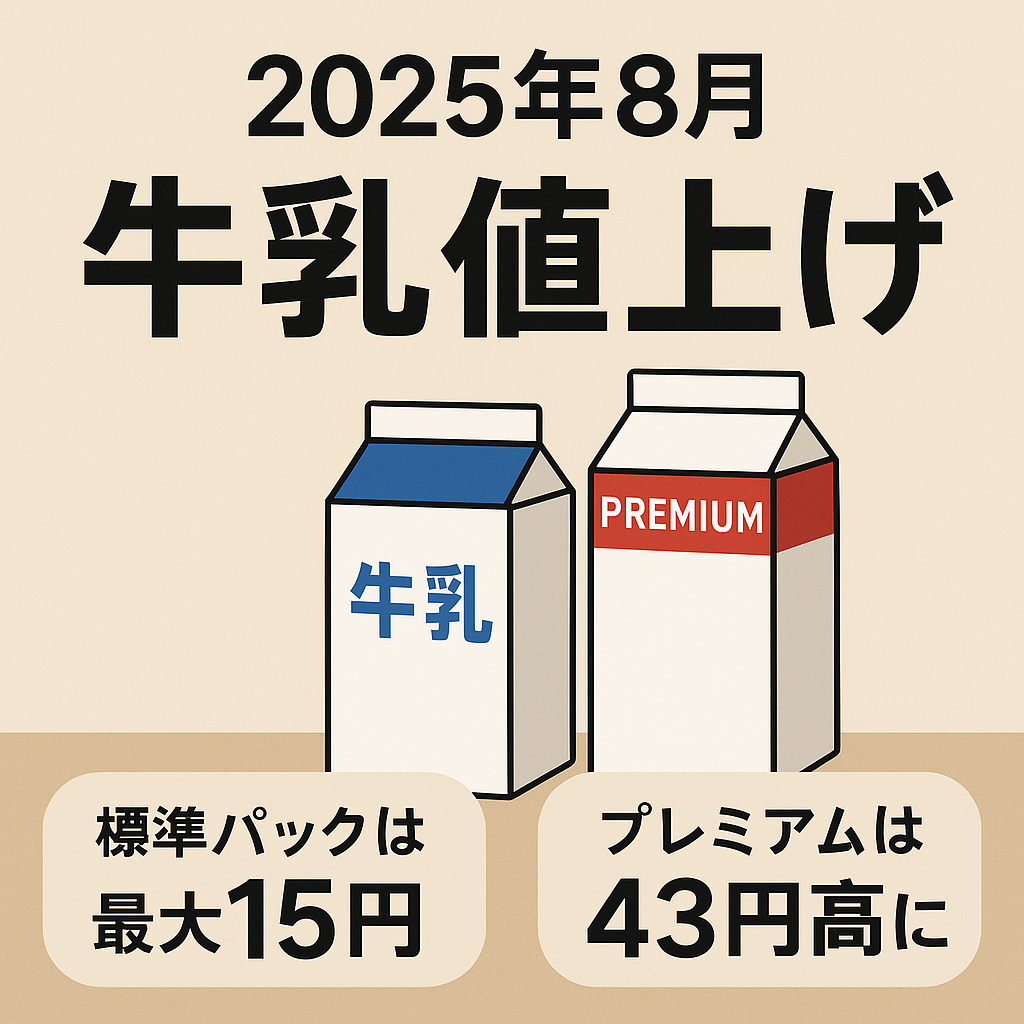
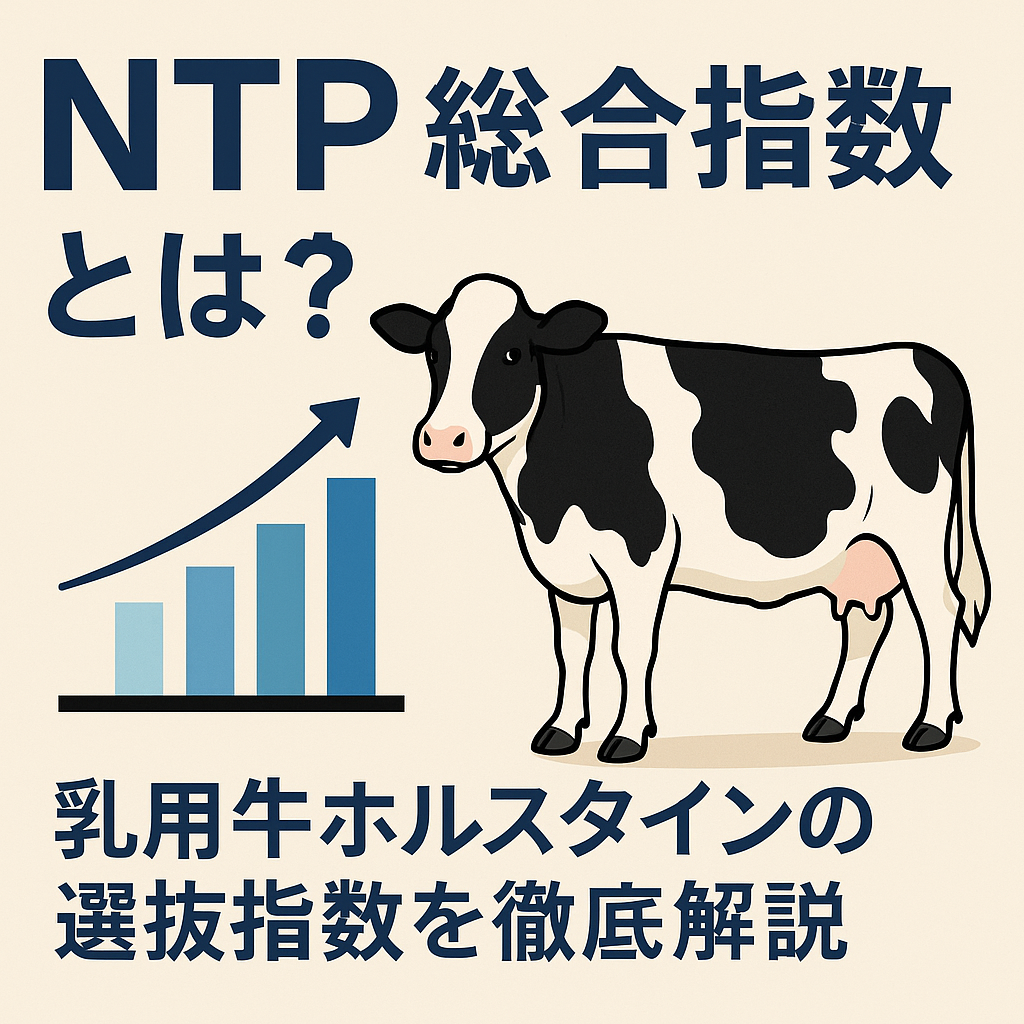
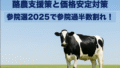
コメント