MUN値は乳牛のタンパク質とエネルギーのバランスを示す重要指標です。適正なMUN管理は乳量・乳成分・繁殖成績の向上、そして窒素排出削減につながります。本記事では測定方法、目安値、高値/低値の原因と現場でできる具体的対策を分かりやすく紹介します。

乳牛のタンパク質とエネルギーのバランスを示す重要な数値です。
1. MUN値とは?(基本の理解)
MUN(Milk Urea Nitrogen、乳中尿素窒素)は、乳中に含まれる尿素窒素量を示す指標です。畜産栄養学的には、ルーメン(第一胃)で分解されたタンパク質由来のアンモニアが肝臓で尿素に変換され、血中を経て乳中に移行したものと考えられます。したがって、MUNは牛群のタンパク質とエネルギーのバランスを反映する簡便なモニタリング指標になります。

第一胃で分解されたタンパク質由来のアンモニアが血中を経て乳中に移行します。

2. MUNの測定方法とデータの読み方
測定はバルク乳(タンク全体)と個体乳の二通りが一般的です。牛群検定や月次のミルク検査結果で把握できるため、定期的な記録が重要です。
目安値(一般的指標)
| 対象 | 目安(mg/dl) | 解説 |
|---|---|---|
| 理想レンジ(目標) | 10–14 | 多くの日本の現場で採用される目安。ルーメンのエネルギーとタンパクのバランスが良好。 |
| やや低い | 8未満 | 低MUNはタンパク質不足やエネルギー不足を示唆。繁殖障害リスクあり。 |
| 高い | 18以上 | 過剰タンパクやルーメンアンモニアの増加。乳量低下や窒素排出増の可能性。 |
※地域や飼料体系によって多少変動します。チモシー主体の地域はやや低め、濃厚飼料依存の群は高めに出る傾向があります。

過剰タンパクやルーメンアンモニアの増加で、乳量低下や窒素排出増加の可能性。

3. MUNが高い場合:原因と現場対策
高MUNの主な原因と対応は以下の通りです。
- 原因1:飼料の粗タンパク(CP)が過剰、またはルーメン分解性タンパク(RDP)が多い。
- 原因2:ルーメンでのエネルギー不足によりアンモニアが有効利用されず尿素へ移行。
- 原因3:給餌タイミングやTMR混合不良で発酵バランスが崩れる。
現場でできる改善策
- 飼料成分の見直し:バイパス蛋白(RUP)を増やし、RDPを調整。CP全体を適正化する。
- エネルギー供給の最適化:発酵性の高い炭水化物を適切に配合してルーメン微生物がタンパクを効率利用できるようにする。
- 給餌管理:TMRの均一化、給餌回数の再考、分離飼料のチェック。
- 現場計測:一定期間ごと(例:月1回)のバルク測定と個体フォローを組み合わせる。

粗タンパク(CP)やルーメン分解性タンパク(RDP)が多いと尿素に移行しやすくなります。
4. MUNが低い場合:原因と対策
低MUNは一見良さそうですが、過度に低いと繁殖成績や乳タンパクに悪影響が出ます。
- 原因例:粗蛋白不足、粗飼料の低品質、あるいは過剰なエネルギー投与でルーメン微生物が相対的にタンパクを使わない状態。
改善策
- 粗飼料の質改善:採草時期や品種の見直し、乾草の保存管理改善。
- 飼料タンパクの補正:必要に応じて総CP%を上げる、もしくは発酵性の良い飼料を併用してルーメン同化率を高める。
- 個体管理:泌乳段階に応じた給餌(初期は低め・最盛期はやや高め)を行う。

過度に低いと繁殖成績や乳タンパクに悪影響があります。
5. 実践的チェックリスト(現場ですぐ使える)
- バルクMUNを月1回は確認し、異常値が出たら個体検査へ移行。
- TMRのサンプルを定期採取してRDP・RUP・CPを確認。
- 給餌タイミング・給与量の記録を継続して変化を追う。
- 繁殖成績(受胎率、空胎日数)とMUNの相関を半年単位で分析。
- 繁殖管理の改善と同時にMUNの改善が見られるかを評価。

6. ケーススタディ:飼料調整でMUNを改善した事例(実践例)
(例)ある牧場では、バルクMUNが平均16mg/dlであり、受胎率低下と乳タンパクの変動が見られました。実施した対策:
- RDPを減らしバイパス蛋白を導入(RUP比率を上昇)。
- 発酵性炭水化物を適正化しルーメンエネルギーを向上。
- 給餌回数を2回から3回へ増やし食欲と醗酵安定を図る。
結果:3か月でバルクMUNは12–13mg/dlへ低下、受胎率が改善し乳タンパクも安定化しました。
このように、データに基づく段階的な調整が有効です。現場の記録を必ず残しましょう。

ある牧場でバルクMUN平均16mg/dl、受胎率低下と乳タンパク変動が見られました。
7. 2025年の注意点:飼料価格高騰とMUN管理
飼料価格が高止まりする環境では、コストを抑えつつMUNを健全に保つ工夫が必要です。具体的には:
- 自給飼料(粗飼料)を最大限活用して品質を上げる。
- 安価なタンパク源を安易に増やさず、ルーメンで有効に使える配合を検討する。
- 飼料購入前に小ロットでトライアルし、MUNへの影響をモニターする。

粗飼料の品質を上げ、経済的かつ栄養バランスを維持。
8. Q&A
Q1. MUNはどのくらいの間隔で測れば良い?A1. バルクは月1回が目安。異常があれば個体検査を追加。
Q2. MUNだけで飼養管理は判断できる?A2. MUNは有用な指標ですが、乳成分、繁殖成績、ボディコンディションスコア(BCS)など他の指標と併せて判断してください。
Q3. 高MUNで真っ先に確認すべき項目は?A3. 飼料の総CP、RDP比、TMRの混合状態、給餌回数と時間を点検してください。
まとめ(要点)
MUN値は「簡単に測れて使いやすい」酪農経営のモニタリング指標です。10–14mg/dlを目安に、定期測定と記録、飼料のRDP/RUPバランス、エネルギー供給の最適化で乳量・乳成分・繁殖成績の改善が十分期待できます。特に飼料価格が変動する現在、コストと栄養を両立する設計が重要です。まずはバルク測定を継続し、異常時には個体ごとの追加検査と段階的な飼料調整を行ってください。

簡単に測定でき、乳量・乳成分・繁殖成績の改善に役立ちます。
※本記事は一般的な情報に基づく解説です。現場での具体的処方は獣医師・飼料技術者と相談のうえ実施してください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

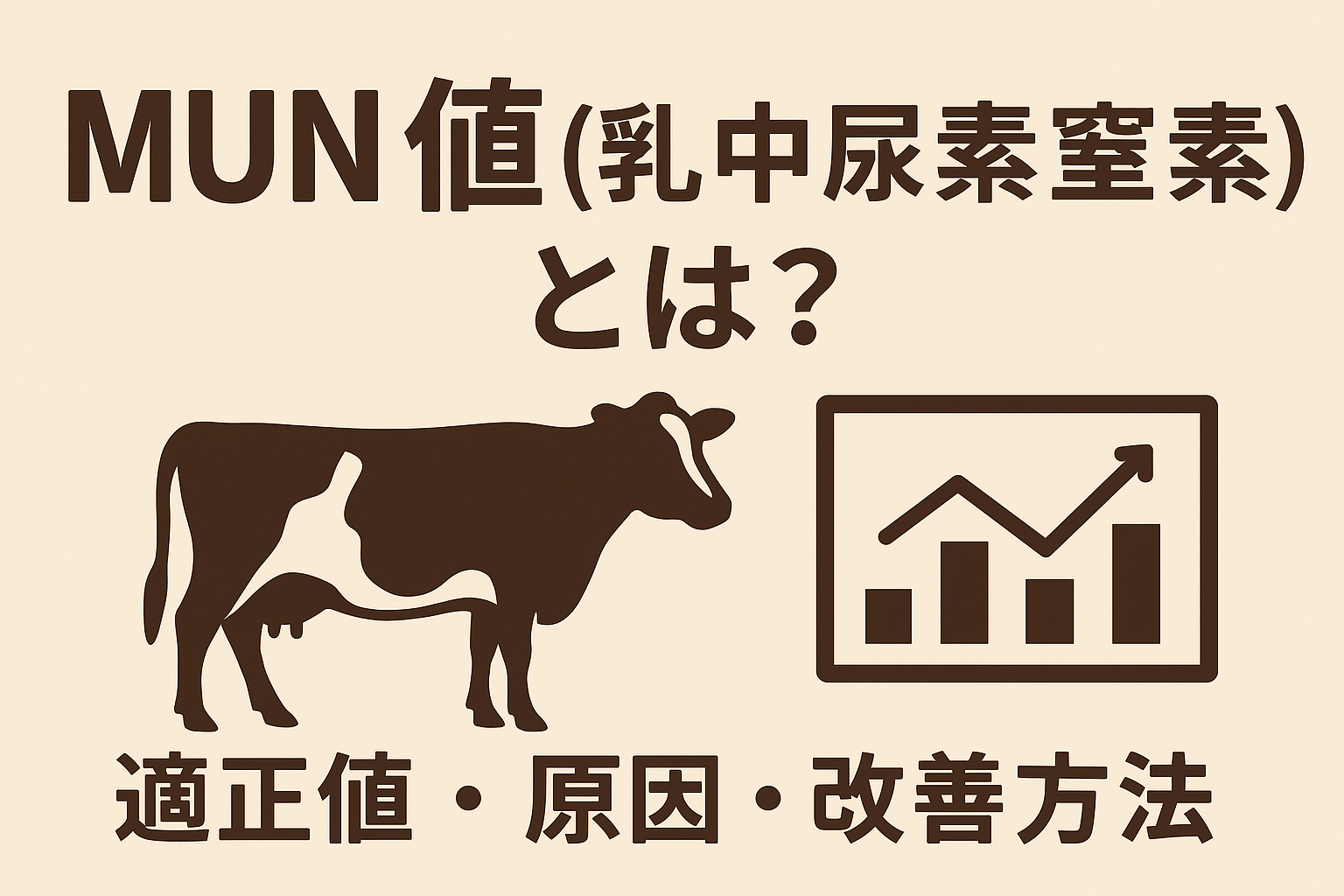
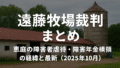
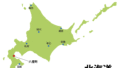
コメント