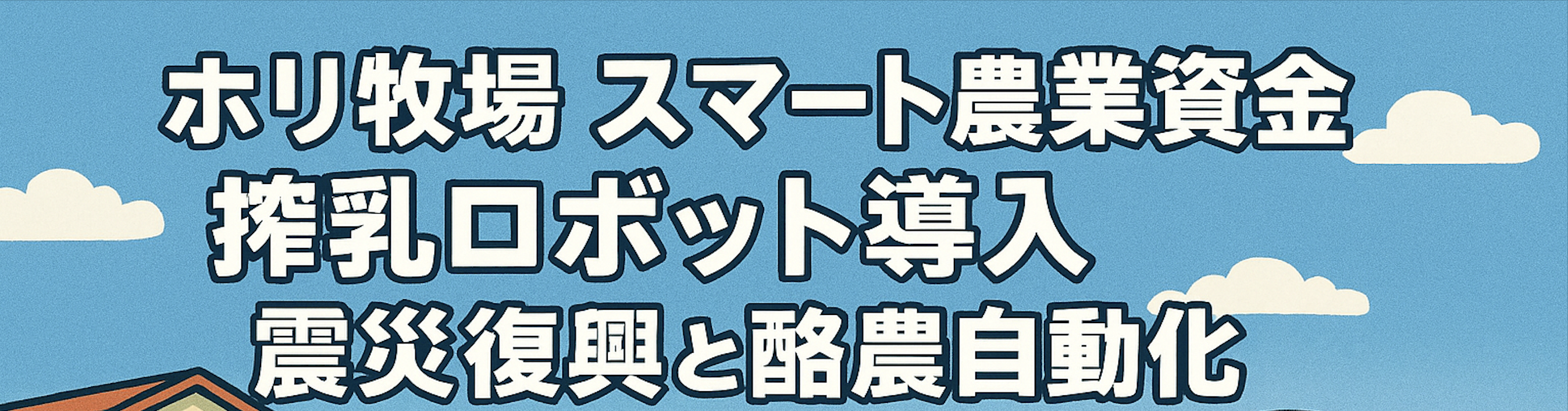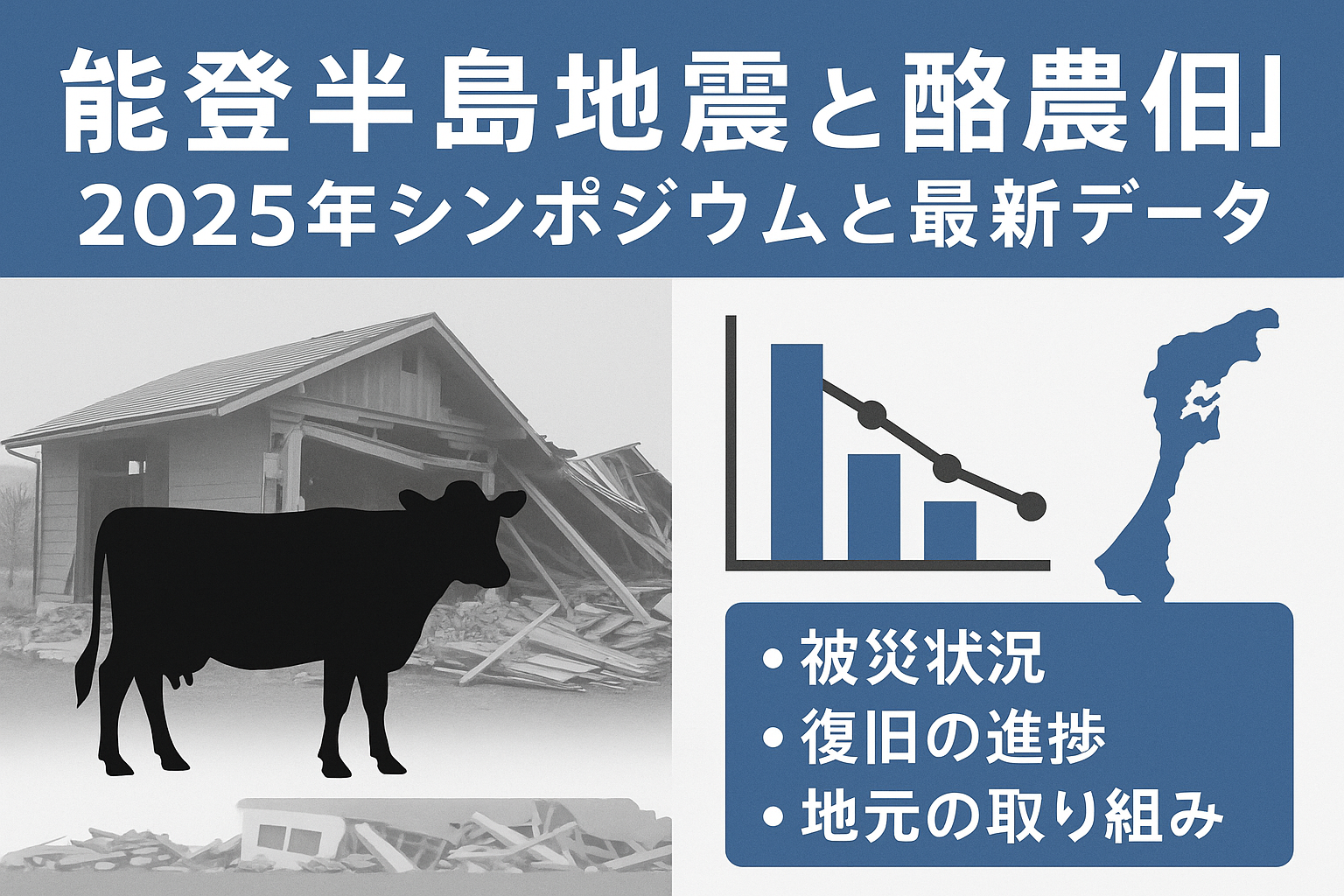石川県内灘町の老舗・ホリ牧場が、報道ベースで「全国初」と伝えられる形でスマート農業資金を活用し、震災復興と酪農の自動化を本格化させました。本記事では、ホリ牧場の導入背景、資金の仕組み、日本政策金融公庫を活用した資金構成、導入した主要装置(搾乳ロボット、乳牛管理ソフト、自動給餌機)と期待される効果について、わかりやすく丁寧に解説します。
なぜホリ牧場はスマート農業資金を選んだのか?(背景)
ホリ牧場は1932年創業、現在は内灘町(河北潟干拓地)で牛舎7棟、約600頭を飼育し年間生乳出荷量は約2815トン(2024年実績)となる石川県内でも大規模な牧場です。2024年の能登半島地震で施設が被災したことを受け、復旧と同時に限られた人員で継続的に生乳を供給するために、従来の手作業中心の生産方式からの転換が急務となりました。
スマート農業資金とは?ホリ牧場の活用ポイント
ここでホリ牧場が利用したのは、日本政策金融公庫等が窓口となる「スマート農業技術活用促進資金」のような低金利融資制度で、農林水産省の「生産方式革新実施計画」の認定を受けることで利用可能な資金です。ホリ牧場は農林水産省認定を受け、約2200万円規模の機器導入費用を低金利で調達しました。
ポイント:資金の活用により初期投資負担を軽減し、搾乳ロボット導入などの先進機器で早期に労力削減と品質安定を図れることが最大の利点です。

導入した主要技術と現場の変化
搾乳ロボット(搾乳自動化装置)
搾乳ロボットは、牛が自ら搾乳ステーションに入ることで自動的に搾乳を行います。これにより、従来必要だった朝晩の搾乳作業が大幅に軽減され、労働時間の平準化・人手不足対策として非常に有効です。
乳牛管理ソフト(データ駆動の飼養管理)
乳牛管理ソフトは、個体ごとの歩行量、採食量、乳量、発情・疾病の兆候などを一元管理。外部獣医師とデータ共有することで早期治療や飼料最適化が可能になり、結果として生乳生産性向上につながります。
自動給餌機(自動給餌システム)
自動給餌機は、定量・定時に正確な飼料を供給できるため、餌ムラを減らし栄養管理を安定化。これもまた生乳品質の向上と廃棄削減に貢献します(自動給餌機)。
導入の効果:震災復興と担い手不足解決を両立
震災復興(震災復興 酪農)の観点では、被災した牛舎の復旧と合わせて最新機器を入れることで、短期間で稼働回復を図れる点が大きいです。また、担い手不足の解決(担い手不足 解決)にも直結します。少ない人員で安定的に生産できれば、経営の継続性が高まり、地域の乳価・ブランド維持にもつながります。
- 労力削減:搾乳・給餌の自動化で日々の作業負担が軽減
- 生産性向上:データ管理で餌や健康管理が最適化される
- 品質安定:牛ごとの管理で高品質な生乳の供給が可能に
- 復興の効率化:復旧と同時に未来型の牧場へ移行

現場の声 — ホリ牧場の思い
ホリ牧場の堀牧人専務は、「現場から機械の導入を求める声が上がっていたので、国から認定されてよかった。復旧を進めながら石川県産の牛乳を全国に届けたい」と述べています。現場の声が導入決定を後押しした点は、同様の事例を検討する他牧場への示唆にもなります。
他牧場が学べる導入チェックリスト
- 現状の作業負荷と人的リスクの棚卸し
- 導入候補機器(搾乳ロボット・自動給餌機・管理ソフト)の選定
- 農林水産省の認定要件や補助・融資制度の確認(日本政策金融公庫等)
- 導入後の運用体制(メンテ・データ連携・外部獣医の役割)を設計
- 地域の震災リスクや復旧計画に連動した設備投資の計画化
石川県(内灘町)と地域への波及効果
ホリ牧場の事例は、石川県—特に内灘町の酪農現場にとってモデルケースになり得ます。北陸エリアでの先行事例として、同様の資金活用やスマート農業化が他牧場へ波及すれば、地域全体の生乳供給力と品質が向上し、復興・ブランド化の双方に好影響を与えるでしょう(スマート農業 石川県)。
まとめ:震災復興を支える“賢い投資”としてのスマート化
- ホリ牧場は石川県内灘町で搾乳ロボットや自動給餌機、乳牛管理ソフトを導入し、スマート農業資金を活用した先行事例となった。
- 導入目的は能登半島地震からの迅速な復旧と、担い手不足による人手負荷の軽減・生乳生産性向上。
- 資金は日本政策金融公庫等の低金利融資と、農林水産省の生産方式革新認定を組み合わせた活用が中心。
- 搾乳自動化とデータ駆動の飼養管理により、労力削減・品質安定・廃棄削減の効果が期待される。
- 他牧場が導入を検討する際は、現状分析→機器選定→認定・融資確認→運用体制(メンテ・獣医連携)を順に整えることが重要。
ホリ牧場のスマート農業資金活用(全国初と報道される事例)は、震災復興(能登半島地震 復旧)と酪農自動化の両立を目指した現場主導の挑戦です。搾乳ロボット導入、乳牛管理ソフトの活用、自動給餌機による飼養管理の高度化は、担い手不足の解消と生乳生産性向上につながる実効的な手法です。地方の復興と酪農の持続可能性を高める観点から、多くの牧場で参考にできる事例と言えます。
※本記事は企業・行政発表および報道を基にまとめています。記事内の「全国初」の表現は報道ベースの表記です。最新の情報や公式発表は各機関(農林水産省・日本政策金融公庫・ホリ牧場)をご確認ください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。