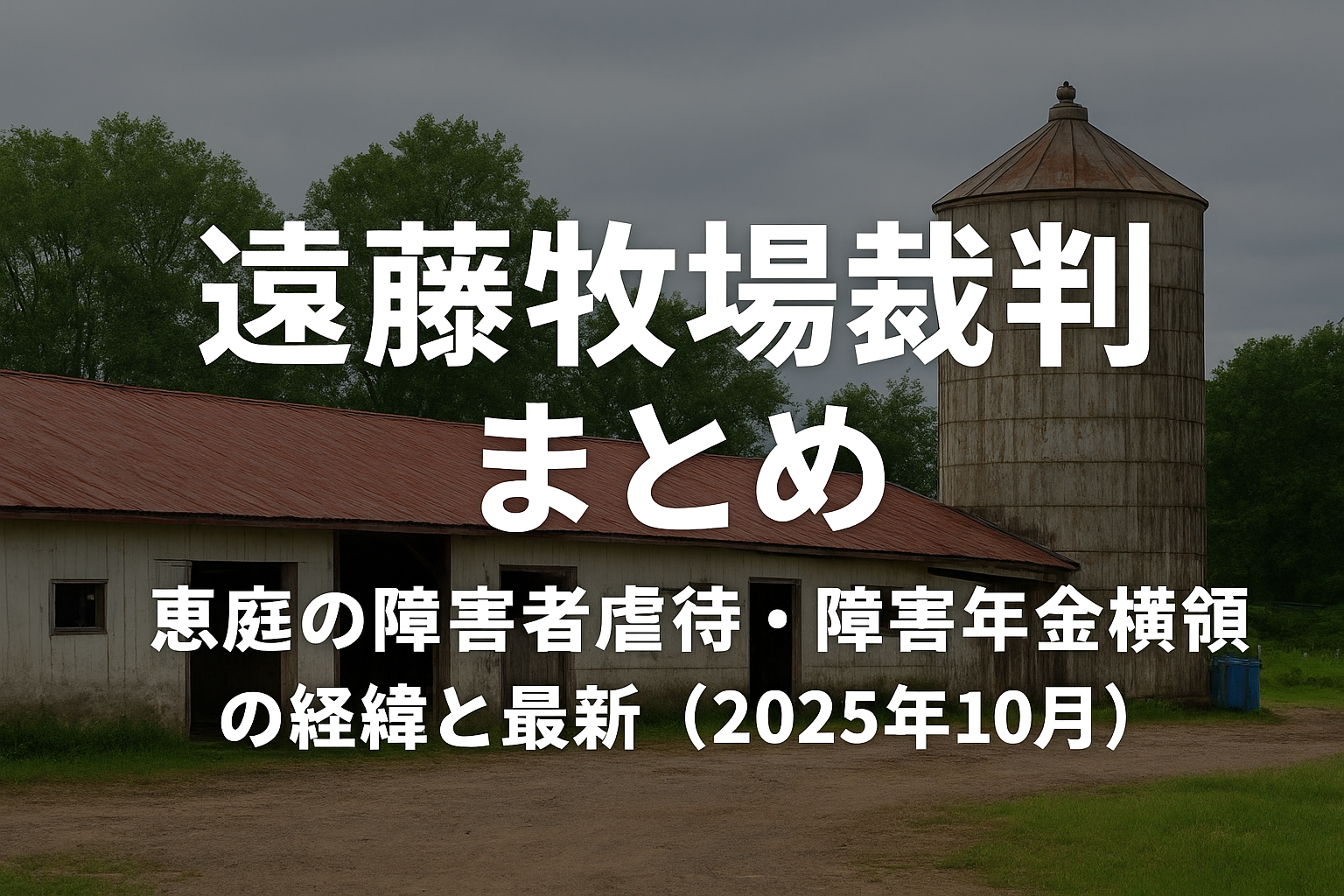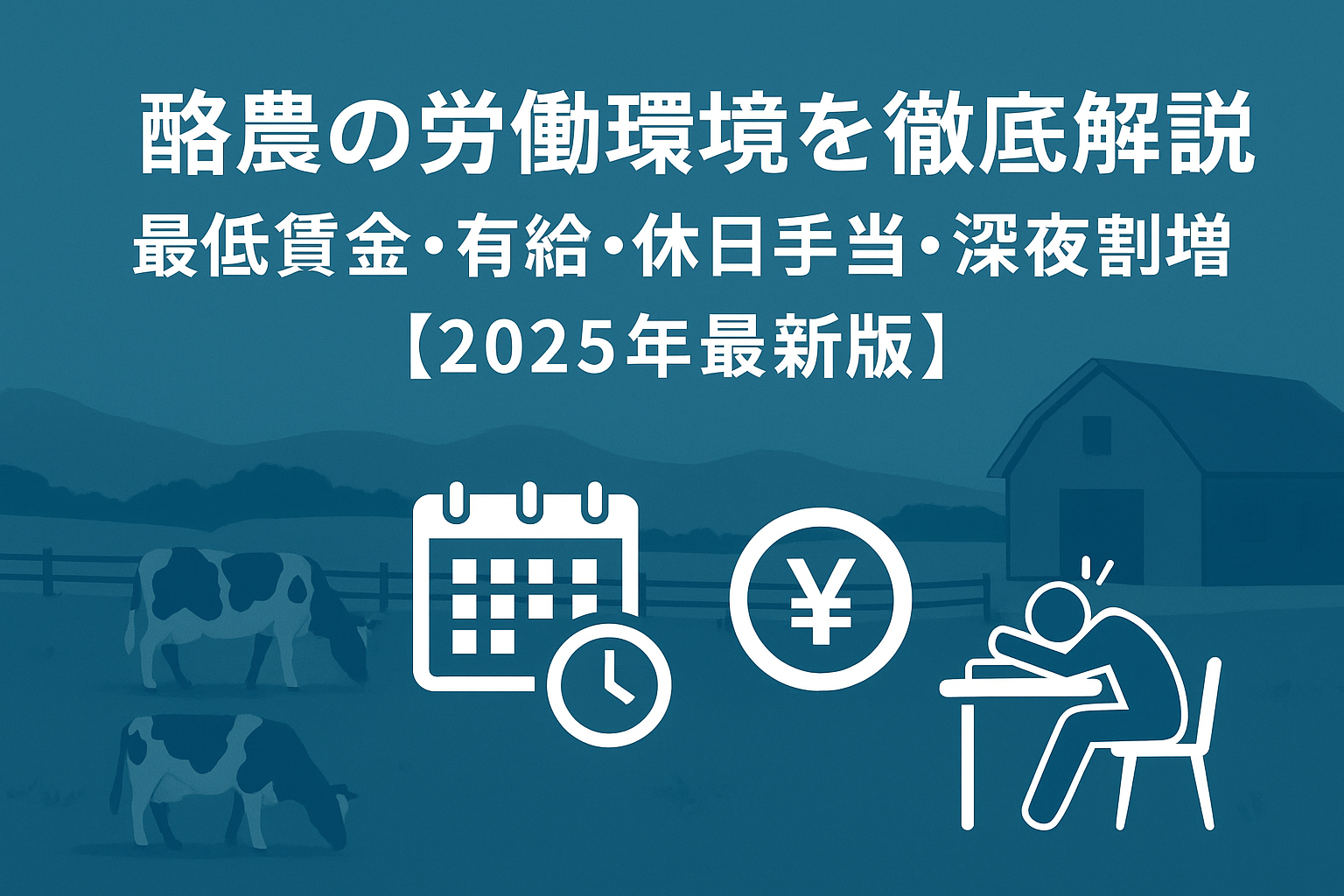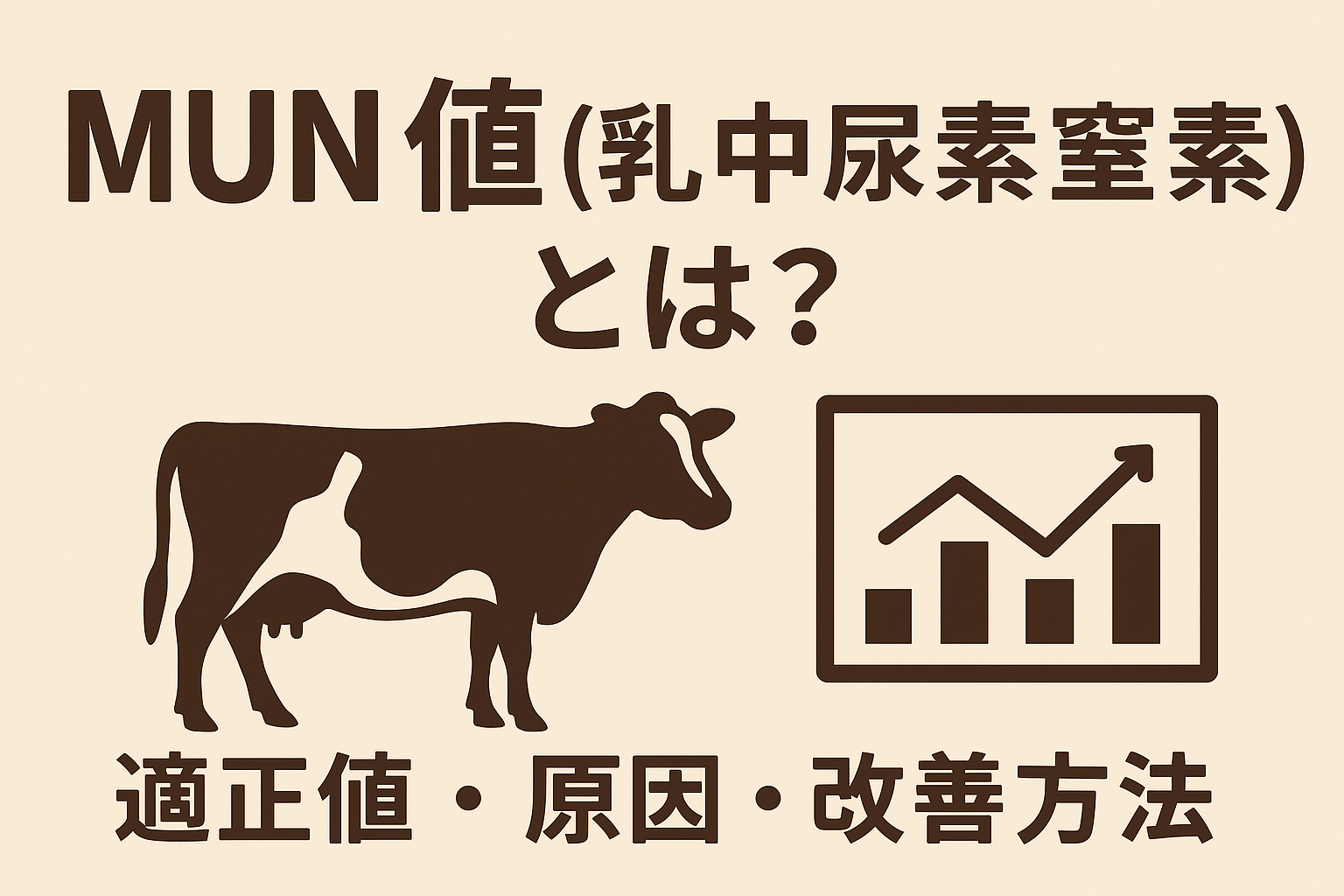北海道恵庭市の遠藤牧場をめぐる訴訟では、知的障害のある元従業員3人が牧場側と恵庭市に対し、長年にわたる過酷な「住み込み労働」や、支給された障害年金の着服(横領)などを主張しており、損害賠償を求める係争が札幌地裁で続いています。2025年10月時点で原告側は本人尋問を視野に、知的障害のある原告らに配慮した尋問方法を求める意見書を裁判所に提出しました。
事案の背景(何が問題とされているか)
原告の3人は、遠藤牧場で住み込みで働きながら給与の未払いや休みなしの長時間労働、プレハブ小屋での劣悪な生活環境を強いられたと主張しています。また、支給された障害年金の相当額が牧場側により管理・流用された疑いがあり、原告側はこれを横領と位置づけています。裁判では事実関係・金銭の流れ・行政の対応が主な争点です。
重要な数値・事実(確認済みの公的情報)
- 訴訟の管轄:札幌地方裁判所(事件番号は公表資料を参照)。提訴日は令和5年(2023年)8月24日(訴状受理:同年9月21日)。
- 原告側は複数の金額(賃金未払、障害年金流用など)を根拠に総額の損害賠償を請求している(報道では総額に関する表現があるため、判決・確定資料での最終数値が参照されるまで「請求額」扱いで表記します)。
- 裁判では、牧場側による労災補償金(約45万円相当)の不正請求疑惑や、原告らの口座からの引き出し(報道では100万円・車購入の疑い等)が指摘されています。
直近の進展(本人尋問に向けた「意見書」提出)
2025年10月17日、原告側弁護団は「本人尋問に際して知的障害を持つ原告への尋問方法に配慮すること」を求める意見書を提出しました。求められている合理的配慮は、質問の簡素化、通訳(手話等)が必要な場合の公費負担の検討、尋問手続きでの精神的負担軽減策などです。原告側は本人尋問を通じて長年にわたる被害実態を法廷で明らかにしたいとの立場を示しています。
行政(恵庭市)の立場と争点
恵庭市は公式に「通報がなかったため当時は虐待と認識しなかった」などと説明し、隠ぺいの疑いを否定しています。一方で原告側は、牧場主が地域で影響力のある立場にあった点を挙げ、行政対応の適切性・監督責任を問い直しています。恵庭市は口頭弁論で証拠書類を提出するなど応訴しています。
酪農現場の視点:なぜ「住み込み」はリスクになり得るのか
酪農の実務では、日常的に牛の世話・搾乳・飼料管理が行われ、早朝・深夜の労働が発生します。適切な労務管理と生活支援(給与の明示、外部との接点、定期的な健康確認、社会保険の整備など)がなされていれば問題は回避されますが、住み込みで外部との接触が極端に制限されると「監視」「連絡」の仕組みが機能せず、悪用される余地が生まれます。現場視点の具体策としては、賃金の定期振込・口座管理の透明化、外部監査の導入、自治体による現地調査の迅速化などが考えられます。
法的に注目すべき点(争点の整理)
- 労働関係性の認定:住み込みであることと労働契約の有無、使用者責任の所在。
- 経済的虐待・私文書偽造等の適用可能性:年金や通帳の管理・不正引出があった場合の刑事・民事上の責任。
- 行政の監督責任:通報義務・調査義務の履行有無と、公的支援のあり方。
これらは裁判を通じて事実認定されるべき事項であり、判決は今後の制度運用や自治体対応にも影響を及ぼす可能性があります。
今後の注目点(ウォッチリスト)
- 本人尋問の実施可否とその運用(配慮の度合い)。
- 裁判所での証拠開示状況(銀行取引・年金支給記録等)。
- 和解の動きまたは最終判決の内容(使用者責任・自治体の責任判断)。
- 本事案が他地域の支援現場に与える影響(制度見直しの議論)。
関連記事
牧場バイトで鬱になりかけた話
参考資料(主な出典)
- HTB(北海道テレビ):「原告側が本人尋問へ向け障害者への質問など配慮求める意見書を提出」2025/10/17。
- 恵庭市公式:「恵庭市に対する民事訴訟の応訴について」(広報・PDF)— 提訴日・口頭弁論等の公的記録。
- 弁護士系報道(ben54 / 弁護士JP):労災補償金45万円の不正請求疑惑など(2025年5月報道)。
- HTBドキュメンタリー映像(「テレメンタリー2024 沈黙の搾取」など)— 現場取材映像のアーカイブ。
編集後記:この事件は、個別の民事紛争を越えて、障害のある人が働き暮らす現場で「どうやって権利と安全を守るか」を問い直す契機です。酪農という地域産業の中でも起こり得る課題として、業界・支援・行政が協力して再発防止に取り組むことが求められます。
(注)この記事は報道・公的資料を基に作成しています。裁判は係争中のため、事実関係や金額は今後の審理・判決で変更される可能性があります。判決確定後の公式情報を優先してください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。