2024年1月1日に発生した能登半島地震は、石川県能登町の酪農家に深刻な打撃を与えました。農場建屋の倒壊や飼料供給ルートの寸断、乳生産量の激減など、多くの課題が浮き彫りになりました。しかし、地元酪農家や関係機関が一丸となり、復旧への歩みを着実に進めています。本記事では、被災から復旧までの経緯をデータや現地シンポジウムの議論を交えながら解説します。

2024年の能登半島地震、酪農家にも甚大な影響が…
1. 背景:能登半島地震と酪農への影響
2024年1月1日16時10分、マグニチュード6.8の能登半島地震が発生。能登町を中心に農場建屋が大規模に損壊し、停電や道路寸断により乳製品の出荷が一時停止しました。とくに被害の大きかった西出牧場では、搾乳牛舎が半壊、育成牛舎が全壊するなど、飼養頭数の維持が困難になる事態に陥りました。
被災直後の乳生産は、前年同月比で約25%にまで落ち込み、地元JAが運行する出荷ルートは従来の3ルートから1ルートに削減され、運転手不足も重なり供給網が逼迫しました。

乳生産量が25%まで激減…出荷もままならない状況に
2. 被災状況と数値データ
| 地域 | 地震前(2023年11月) | 地震後(2024年11月予測) |
|---|---|---|
| 能登町 | 酪農戸数:6戸 | 酪農戸数:4戸 |
| 珠洲市 | 酪農戸数:5戸 | 酪農戸数:4戸 |
| 穴水町 | 酪農戸数:1戸 | 酪農戸数:1戸 |
| 輪島市 | 酪農戸数:0戸 | 酪農戸数:0戸 |
- 2024年1月の乳生産量:前年同月比約25%
- 乳廃棄量:9,100kg(地震直後)
- 負傷家畜:2頭
これらのデータから、地域全体で生産基盤が縮小し、再建までには相当な時間と労力を要すると予測されました。

たった1カ月で9,100kgもの生乳が廃棄に
3. 2025年7月12日シンポジウムの全貌
石川県能登町役場にて、一般社団法人熱中学園主催による復旧シンポジウム「牛とともに能登を再建しよう」が開催されました。オンライン参加を含め約70名が出席し、講師や地元酪農家が一堂に会しました。
- 講師:原田秀夫氏(一般財団法人畜産環境整備機構 副会長)
- 登壇者:平林将氏(能登牧場 執行役員)、西出譲氏(西出牧場 代表)
- テーマ:地震後の復旧状況共有、関連産業との連携、持続可能な酪農モデル
登壇者からは、「復旧は進んでいるが、かつての生産水準を回復するにはまだ時間が必要」「地元飼料自給に向けたデントコーン栽培が鍵を握る」といった意見が出され、集約された議論は今後の復興方針に大きく影響を与えるものとなりました。

オンライン含め約70名が参加。関心の高さが伝わります
4. 現在の復旧状況と最新データ
2025年7月現在、能登町の酪農戸数は地震前の6戸→5戸へと徐々に回復傾向にあります。乳生産量は2024年2月以降、断続的な回復を見せ、2025年上半期には地震前の約60%まで戻しました。
- 乳出荷再開時期
- 柴牧場:2024年1月10日
- 西出牧場:2024年1月14日
- 穴水町1農場:2024年9月20日
- 復旧設備
- 可搬型発電機の設置(R6年度予算)
- 使い捨て乳管の導入
- PHEV車による電源確保実験
また、「奥能登営農復旧・復興センター」が農林水産省・県・JA連携で設置され、技術支援や資金面の相談窓口として機能しています。

乳生産量、ついに60%まで回復!前進の証です
5. 地元酪農家の取り組み事例
A. デントコーン栽培による飼料自給
地震で飼料輸送が滞った経験から、能登町内の転作田でデントコーンを栽培。収量は年間約50トンを見込み、地元飼料自給率向上に寄与しています。
B. 小規模農場の連携体制
能登町6戸の農家が共同で堆肥場を運営し、肥料コストを削減。集約化により、災害時のリスク分散も実現しました。
C. 循環型エネルギー利用
PHEV車の100V出力を利用した給電システムを試験運用。牛舎の冷暖房や搾乳機への電力供給に成功し、停電リスクに対する備えを強化しました。

デントコーンで“飼料の地産地消”が進行中!
6. 課題と今後の展望
- 建屋・設備の再構築コスト
- 小規模農家が多く、高額な再建資金の確保が喫緊の課題。
- 労働力不足と後継者問題
- 若手就農者の育成強化と酪農ヘルパーのマッチング支援が求められる。
- 気候変動リスク
- 大雨や台風による二次災害を想定した防災計画の策定が必要。
- 市場競争力の強化
- 地元ブランド化や付加価値乳製品の開発による収益多様化を図る。
今後は、農林水産省・JAの支援を活かしつつ、地元資源を最大限に利用した持続可能な酪農モデルの構築が期待されます。

若手育成と酪農ヘルパーのマッチングで人手不足を解消
まとめ
- 地震直後、能登町の酪農戸数は6戸→4戸に減少し、乳生産量は前年同月比で約25%に落ち込んだ。
- 2025年7月12日のシンポジウムでは、復旧進捗と課題、地元飼料自給や発電対策など多岐にわたる取り組みが共有された。
- 最新データでは酪農戸数は5戸に回復、乳生産は地震前の約60%まで戻している。
- 今後は建屋再建資金、人材確保、防災計画、付加価値製品開発などが鍵となる。
- 行政・JA・農家の連携により、持続可能な再建モデルの確立が期待される。
能登半島地震から1年半が経過し、能登町の酪農復旧は一定の成果を上げています。しかし、完全復旧には建屋再建や人材確保、資金調達など解決すべき課題が山積しています。2025年7月12日のシンポジウムは、地域全体の課題共有と連携強化の契機となり、今後の復興に向けた具体策が生まれつつあります。引き続き、地域・行政・関係機関が一体となり、一歩ずつ着実に再生への道を歩んでいくことが求められます。

シンポジウムで共有された課題と未来への戦略
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

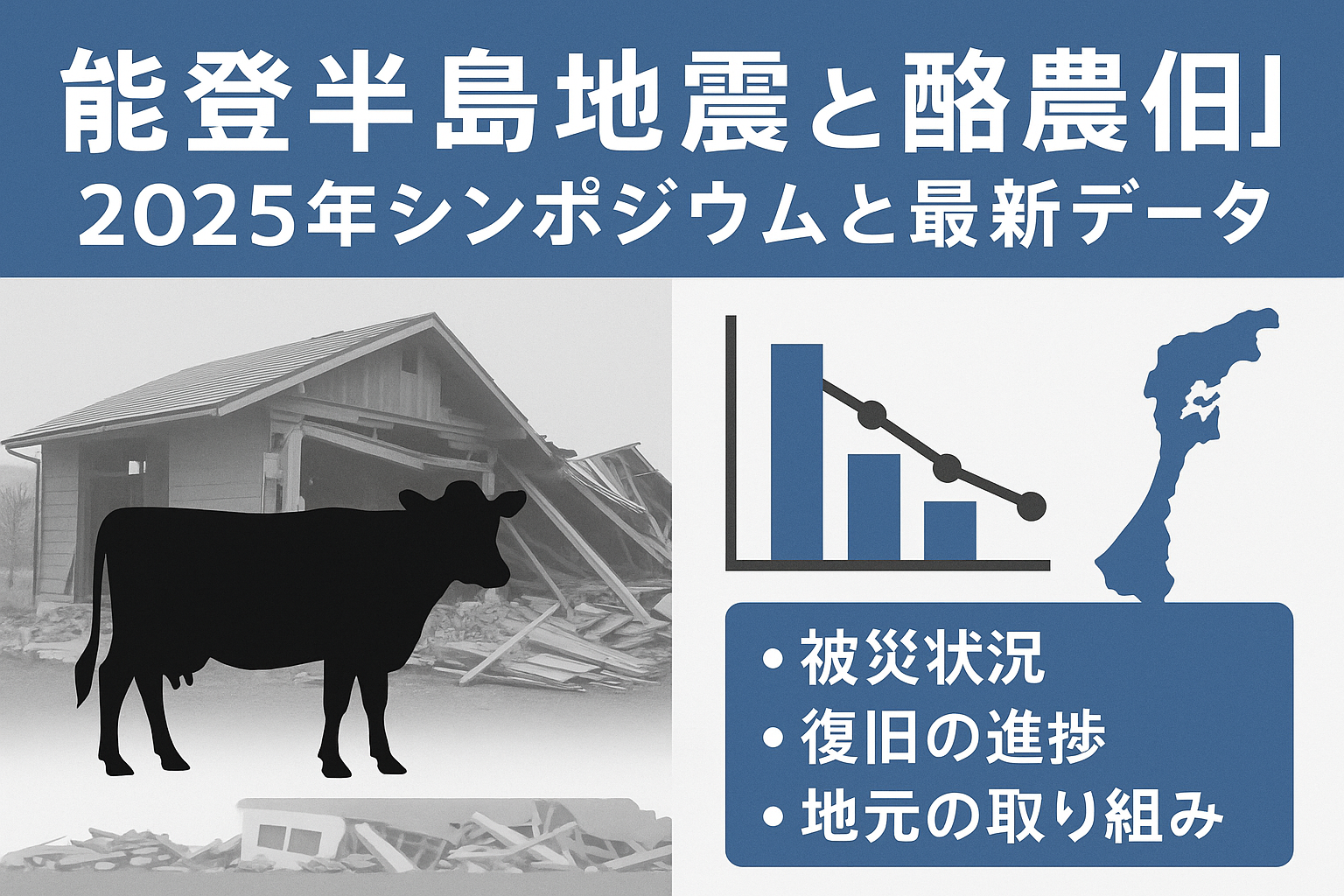
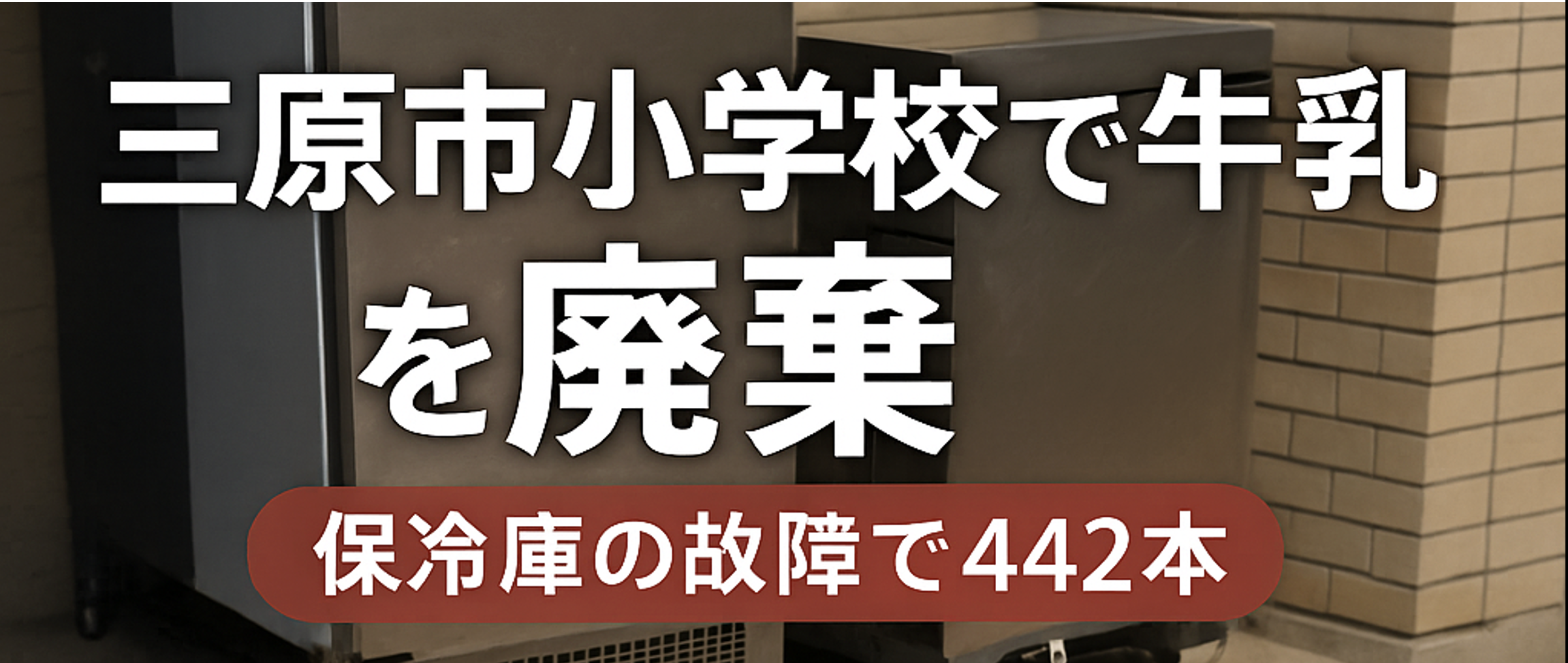
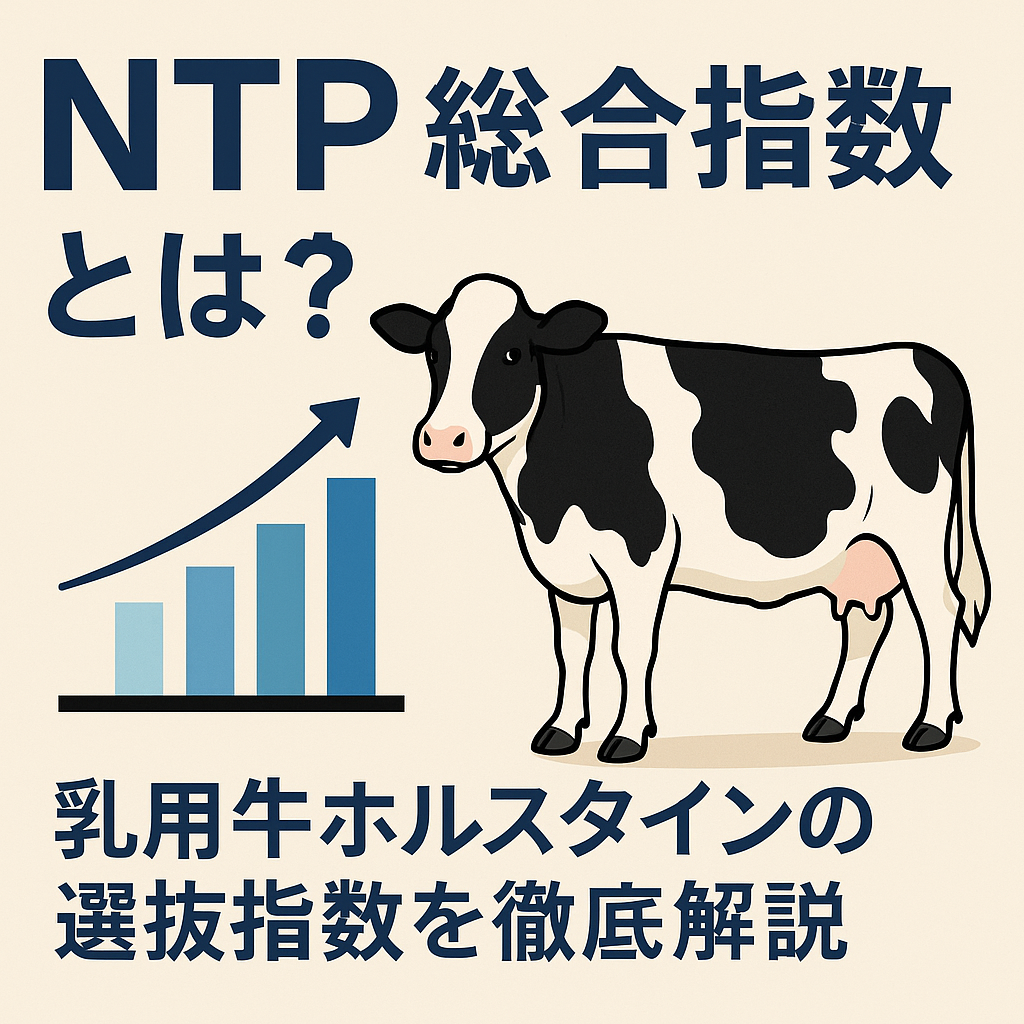
コメント