2025年9月26日、岩手県一関市を拠点とする肥育牧場が、牛の個体識別を義務付ける法令に違反したとして行政指導を受けました。対象は合計269頭。耳標の未装着や届出不備が多く含まれ、食の安全管理・追跡性の観点から重大な問題です。本記事では「何が問題だったのか」を整理し、酪農現場で実務としてすぐ使える再発防止のチェックリストと対応手順を詳しく解説します。
この記事のポイント
- 違反件数:269頭(内訳を表で明示)
- 問題点:耳標の未装着、誤装着、届出不備が中心
- リスク:個体追跡不能によるBSE等の疫学調査支障、ブランド信頼の低下
- 現場対応:具体的な是正ステップと日常管理チェックリストを提示
違反の内訳
検査で確認された問題点の主な内訳は次の通りです。
| 項目 | 頭数(件数) | 内容 |
|---|---|---|
| 耳標未装着 | 37頭 | 出生後に耳標が装着されていない個体が確認 |
| 誤装着 | 1頭 | 耳標が正しい個体に装着されていない疑い |
| 他個体の耳標装着疑い | 9頭 | 識別番号の混同が疑われる事例 |
| 譲渡・死亡時の届出不備 | 222件 | 移動・譲渡・死亡の届出が適切に行われていない |
| 合計 | 269頭(件) | 立入検査により確認された全体数 |
なぜ「牛の個体識別」は重要なのか?
牛の個体識別は、出生から出荷・死亡まで個々の牛を追跡するための仕組みです。具体的な役割は下の3つ:
- 疫病の追跡:万が一疾患が発生したときに、どの個体がいつどこへ移動したかを追えて、拡散経路を特定できます。
- 食品安全の担保:牛肉や牛乳の由来を明確にできることで、消費者への説明責任を果たします。
- ブランド信頼の維持:産地・生産過程が追えることは、ブランド牛の価値に直結します。
現場での注意点:耳標の装着ミスや届出の遅れは「人為的ミス」が多く、手順の標準化とチェックの仕組みが有効です。
今回の行政処分の意図と現場への要求
行政が行う催告・指導は、まずは是正を求める段階です。主に求められることは:
- 管理体制の整備(誰が、いつ、どの情報を記録・確認するか)
- 届出の再点検と遡及処理(未届出分の速やかな登録)
- 従業員教育の徹底(制度の意図と日々の実務手順の共有)
現場ですぐ使える:再発防止チェックリスト(実務向け)
以下は、日常業務に組み込みやすい簡単なチェックリストです。印刷して現場に貼ることを想定しています。
- 耳標装着チェック(出生時):出生後24時間以内に装着を確認 → 装着者のサインを台帳に記入。
- 耳標読取ルール:読み取りは2名で実施し、番号を入力した後に写真を保存(スマホ可)。
- 移動・譲渡・死亡の届出:発生から48時間以内に申告(担当者は連絡先を明確化)。
- 月次の個体照合:台帳と現物の突合を月1回実施、結果をログ保管。
- 社員教育:年2回以上の制度理解研修と、新人に対するOJTチェックリスト。
- 監査トレース:重要処理(届出・番号修正)は必ず履歴を残す(誰が何をしたか)。
テンプレ:移動届出の最短フロー(6ステップ)
- 移動決定 → 書面(またはシステム)で事前記録
- 移動当日:移動先・個体IDを最終確認(2名)
- 移動完了後48時間以内に届出
- 届出後、届出番号を台帳に反映
- 月次で届出済み一覧と台帳を突合
- 不一致があれば即時是正し、原因を報告・記録
ブランド牛・販売面での影響と取り得る対応
個体識別に関する問題は、消費者の信頼や取引先との関係に影響します。対応策の要点は次のとおりです。
- 透明性の確保:公式発表で事実と対策を明確に示す(誤解の余地を減らす)。
- 取引先との連携:主要流通先・取引先に事情説明と再発防止策を提示し、信頼回復を図る。
- 早期の改善報告:改善措置がまとまったら、第三者(専門家)による確認や報告書を公表すると効果的。
現場でよくある疑問(FAQ)
Q1:耳標が外れていたらどうする?
A:まずは個体の確認(写真・耳の特徴・記録照合)を実施し、識別番号を再確認。元の番号が不明な場合は、届け出先に相談し、誤認リスクを下げるための記録を残すことが重要です。
Q2:届出忘れが大量に見つかったら?
A:発見した範囲を速やかに整理し、優先順位(健康リスクが高い個体→届出に影響する移動)で対応。行政に事情説明したうえで、遡及届出のスケジュールを提示します。
Q3:罰則はあるの?
A:法令違反に対しては是正指導・催告がまず行われ、重大または悪質な場合はさらに行政処分が検討されます。日常的な運用体制の強化でリスクを下げることが先決です。
まとめ(現場に必要な次のアクション)
- 発生事案:いわて門崎丑牧場で立入検査により269頭の個体識別関連違反が確認(耳標未装着・誤装着・他個体の耳標装着疑い・届出不備など)。
- 行政対応:農林水産省(関係局)による催告・指導で、管理体制の整備と届出の是正、従業員教育の徹底が求められている。
- リスク:個体追跡が困難になると疫学調査(BSE等)や流通の信頼性に重大な影響を与え、ブランド牛の価値低下も懸念される。
- 現場対策(即実行):未届出・未装着の早期リスト化→優先是正、耳標装着の手順標準化、48時間以内の届出ルール、月次の台帳突合、担当者の明確化と研修。
- 対応のポイント:ルールは簡潔にし、記録(写真・署名)を残す運用を徹底すること。改善状況は外部に分かりやすく報告すると信頼回復に有効。
- 次のアクション提案:現場チェックリスト・届出ワークフロー図・月次チェックシートのテンプレを作成し、早期に運用開始すること。
今回の事例は「人為的な管理ミス」が主要因であることが多く、手順の明確化・記録の徹底・従業員教育が効果的です。まずは下の3つを実行してください。
- 未届出・未装着のリストを作り、優先順位を付けて是正処理を開始する。
- 耳標装着・届出フローを文書化し、担当者を明確にする。
- 月次での記録突合と年次の外部レビュー(可能なら第三者)を導入する。
ワンポイント:現場のルールは複雑にしすぎると運用されません。まずは「やらないといけない最低限の手順」を決め、確実に実行できる形に落とし込むことが肝心です。
関連記事
農林水産省(MAFF)と酪農の関係とは?価格安定策・融資制度・環境対策を解説
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。




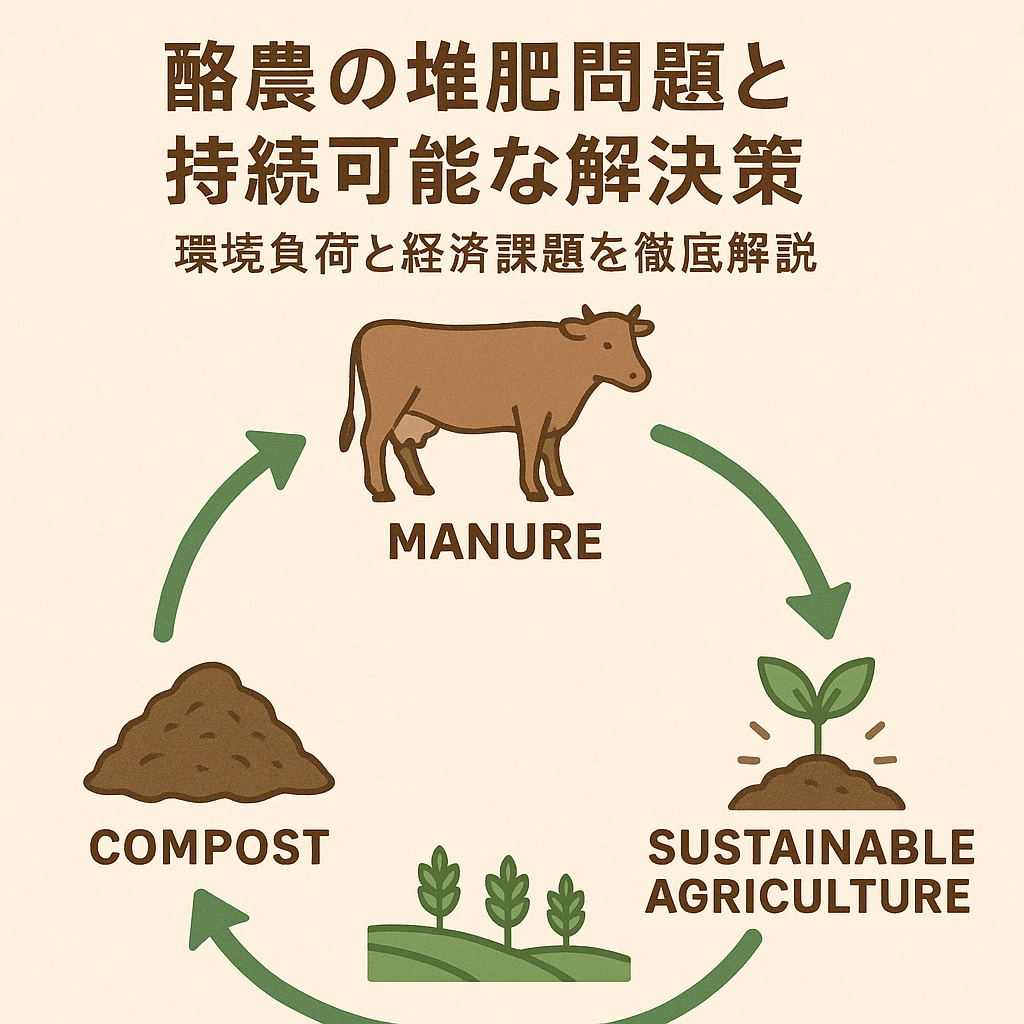
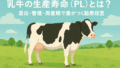
コメント