日本の酪農産業を支える縁の下の力持ち──それが「一般社団法人中央酪農会議」です。1962年の設立以来、生乳の安定供給や品質向上、価格の安定化、需要拡大まで多岐にわたる使命を担い、最近では能登半島地震の支援や酪農教育にも力を注いでいます。本記事では、組織の歴史から最新の市場データ、具体的な支援活動まで、わかりやすくご紹介します。

中央酪農会議は1962年設立の日本酪農を支える重要組織です。
はじめに:中央酪農会議とは?
一般社団法人中央酪農会議(Japan Dairy Council)は、1962年に農林省(現・農林水産省)の通達で設立され、2013年に一般社団法人へ移行しました。東京都千代田区を拠点に、全国の生乳生産者団体をまとめ、以下のような役割を担っています。
- 生乳生産の安定化
- 品質向上・安全性確保
- 牛乳需要の拡大
- 価格の安定化支援
- 酪農教育の推進
酪農家・乳価交渉機関・流通業者が一体となり「協同組織による受託販売」を行うことで、国内生乳の需給バランスを保ちつつ、消費者へ安全・安心な牛乳を届ける仕組みを構築しています。

生乳生産の安定化と品質向上、安全性確保を重要な役割としています。
1. 組織の歴史とミッション
1-1. 設立の背景
- 1962年8月8日:加工原料乳の安定供給を目的に設立
- 1966年:指定生乳生産者団体が認定され、組織体制を強化
- 2013年4月1日:一般社団法人へ法人形態を変更
これらの制度変更により、中央酪農会議は“国策と生産者組織の橋渡し役”としての機能を強化。生乳の安定供給・品質管理・価格交渉を一元的に支援しています。

1962年、加工原料乳の安定供給を目指し中央酪農会議が設立されました。
1-2. 主なミッション
- 受託販売の推進
生乳生産者からの委託を受け、原乳の一括販売を行うことで、安定した取引価格を実現。 - 流通の合理化
生乳集荷から製造・流通までのプロセスを最適化し、コスト削減と鮮度保持に貢献。 - 品質向上と安全性
検査体制の強化およびGMP(適正製造規範)の徹底によって、高い品質の原乳を安定供給。 - 需要拡大施策
学校給食や給食用牛乳の普及啓発、国内外マーケットでのプロモーション支援。 - 酪農教育・研修
産地研修会や酪農教育ファームを通じて、技術伝承や次世代人材の育成を図る。

酪農教育ファームや研修会で次世代人材の育成・技術伝承に注力。
2. 日本の酪農業と市場動向
2-1. 生乳生産と酪農家数の推移
日本の国内総農業生産額に占める酪農の割合は約8%。しかし、後継者不足や高齢化の影響で酪農家戸数は年々減少し、2024年末時点で約9,960戸に。2009年の2万4,000戸から半減以下の数値となっています。

持続可能な酪農経営と若手育成が急務となっています。
2-2. 乳製品市場規模の予測
- 2025年:約32.59億ドル(約4,300億円)※Mordor Intelligence調べ
- 2030年予測:年平均4.44%成長で約40.51億ドルに到達見込み
バターや脱脂粉乳の輸出は安定しているものの、国内需要に直結する飲用乳はやや停滞。中央酪農会議は国内需要拡大策として、学校給食や牛乳消費キャンペーンを推進しています。

乳製品市場は今後も持続的な拡大が期待される重要セクターです。
3. 最近の活動と具体的事例
3-1. 能登半島地震(2024年1月1日)の支援
能登半島地震によって被災した酪農家を支援するため、2024年6月24日に北陸乳業協同組合連合会へ救援金・弔慰金を贈呈。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 救援金 | 5,894,495 |
| 弔慰金 | 11,798,390 |
| 合計 | 17,692,885 |
このような支援活動は、被災地の早期復旧と酪農業再建に大きな役割を果たしました。

2024年1月の能登半島地震被災酪農家への支援を実施しました。
3-2. 2025年7月の最新ニュース
- 7月15日:6月分用途別販売実績を公開
- 7月9日:6月下旬の受託乳量を更新
- 7月4日:酪農百科 vol.8掲載、ミルククラブ145号発行
公式サイトの「What’s New」コーナーでは、上記のほかにセミナー案内や統計データの提供も行われています。日々更新される情報は、酪農家だけでなく酪農関連ビジネス、研究者にも有用です。

最新情報は酪農家や関連業界、研究者にとって重要な資源です。
4. 今後の展望と課題
4-1. 課題
- 酪農家戸数の減少:後継者不足対策が急務
- 飼料コストの高騰:安定的な飼料調達ルートの構築
- 気候変動リスク:暑熱ストレスや災害への備え強化

酪農家戸数の減少は後継者不足対策が急務となっています。
4-2. 展望
- 需要拡大のためのプロモーション強化
学校給食以外にも、若年層向けのSNSキャンペーンやパッケージリニューアル支援。 - 品質保証の高度化
ブロックチェーン技術を利用したトレーサビリティシステム導入検討。 - 人材育成と教育支援
産学官連携による研修プログラムやオンライン講座の拡充。

需要拡大に向け、学校給食だけでなく若年層向けSNSキャンペーンも強化中。
まとめ
- 設立と歩み:1962年設立、2013年に一般社団法人へ移行し、国策と生産者をつなぐ役割を強化。
- 主要ミッション:生乳受託販売の推進、流通合理化、品質保証、需要拡大、教育・研修支援など。
- 市場動向:2025年の乳製品市場は約32.6億ドル、2030年には40.5億ドルに成長予測。酪農家数は減少傾向。
- 具体的活動事例:2024年能登半島地震被災地へ約1,769万円の救援金・弔慰金を贈呈。2025年7月には用途別販売実績や研修会情報を更新。
- 今後の展望:後継者不足・飼料高騰・気候変動リスクへの対応、プロモーション強化、トレーサビリティ導入、人材育成の拡充が課題かつチャンス。
中央酪農会議は、「組織的な受託販売」「品質・安全性の徹底」「教育・支援活動」を通じて、日本の酪農業を守り、さらに発展させるキーパーソンです。今後は、少子高齢化や気候変動といった逆風にも立ち向かい、国民の健康を支える「牛乳・乳製品」の安定供給に貢献していく役割が一層期待されます。

中央酪農会議は1962年設立、2013年に一般社団法人へ移行し、国策と生産者をつなぐ重要な役割を担います。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

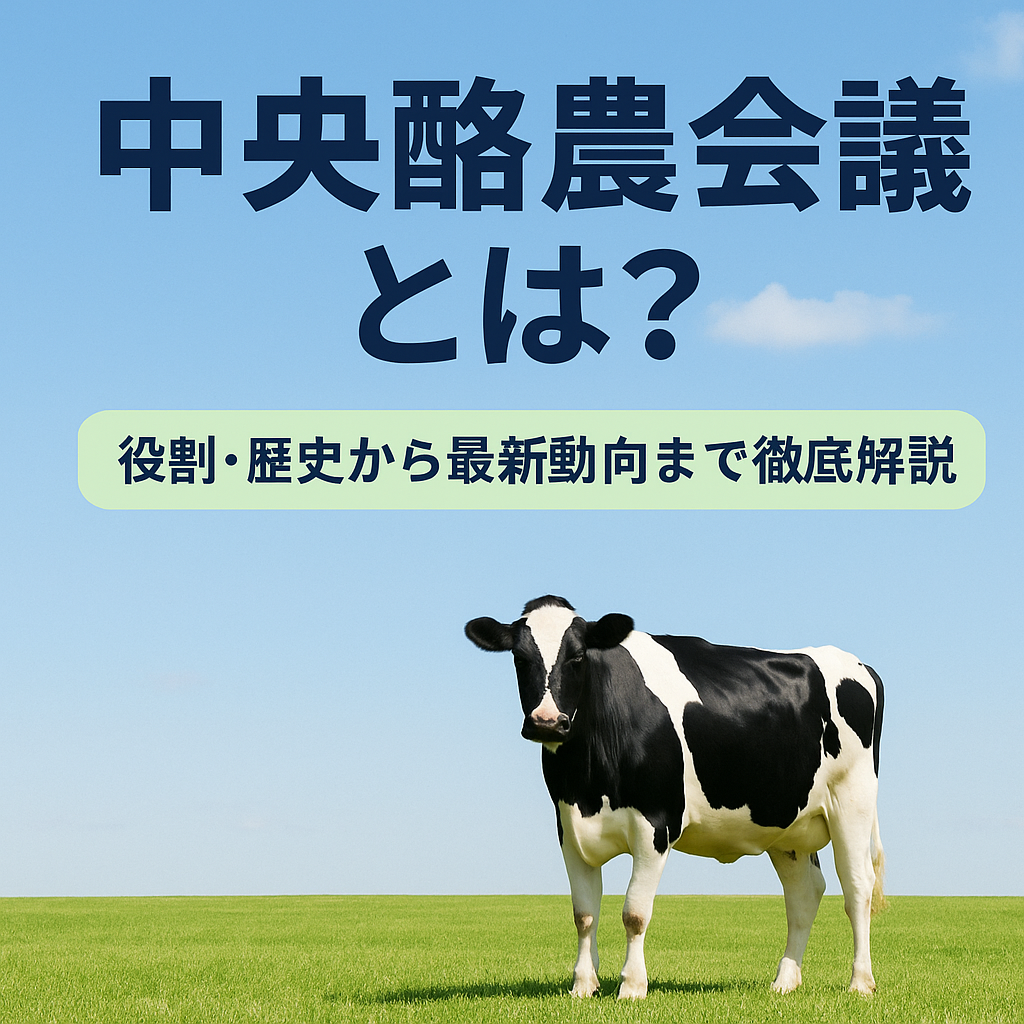

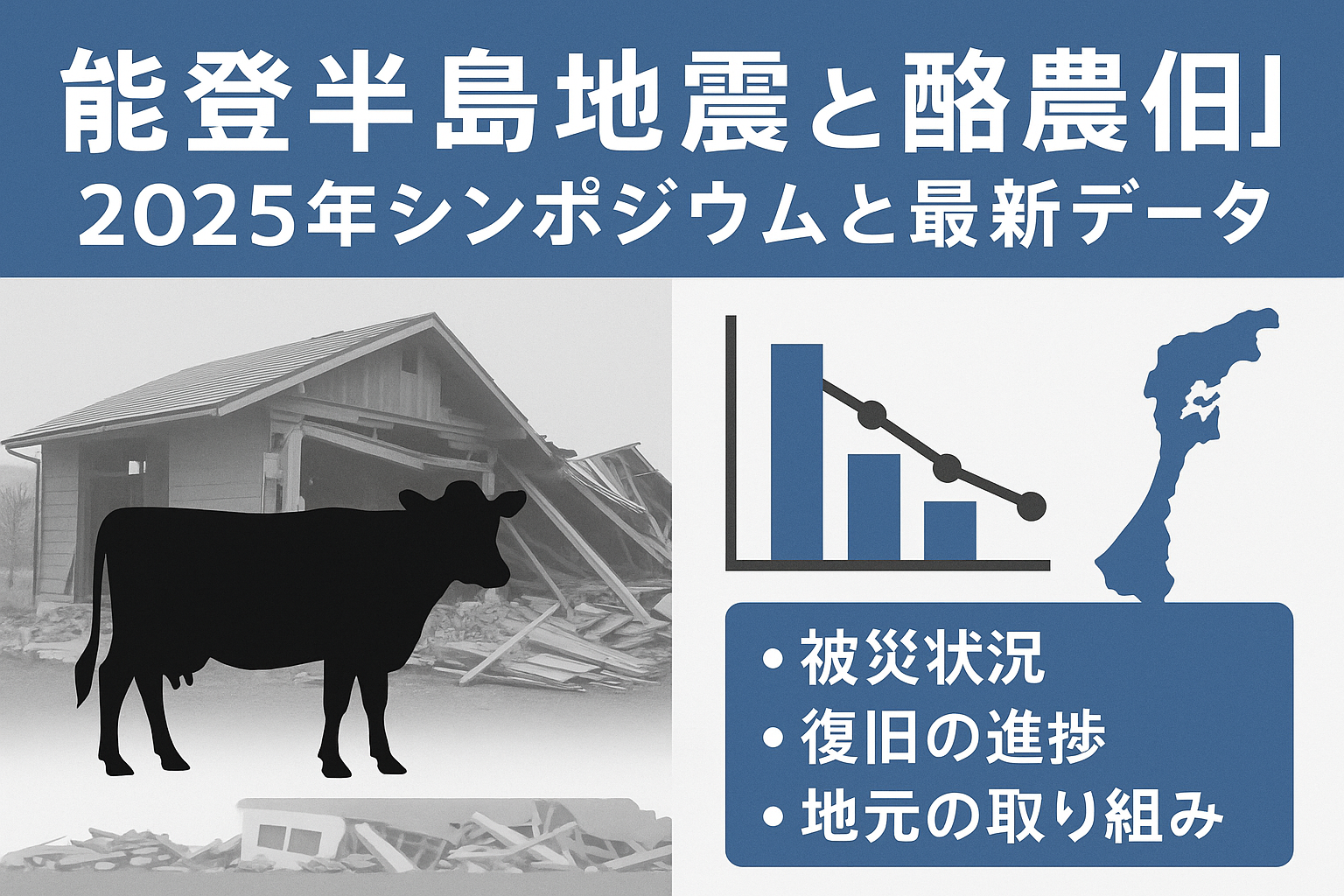
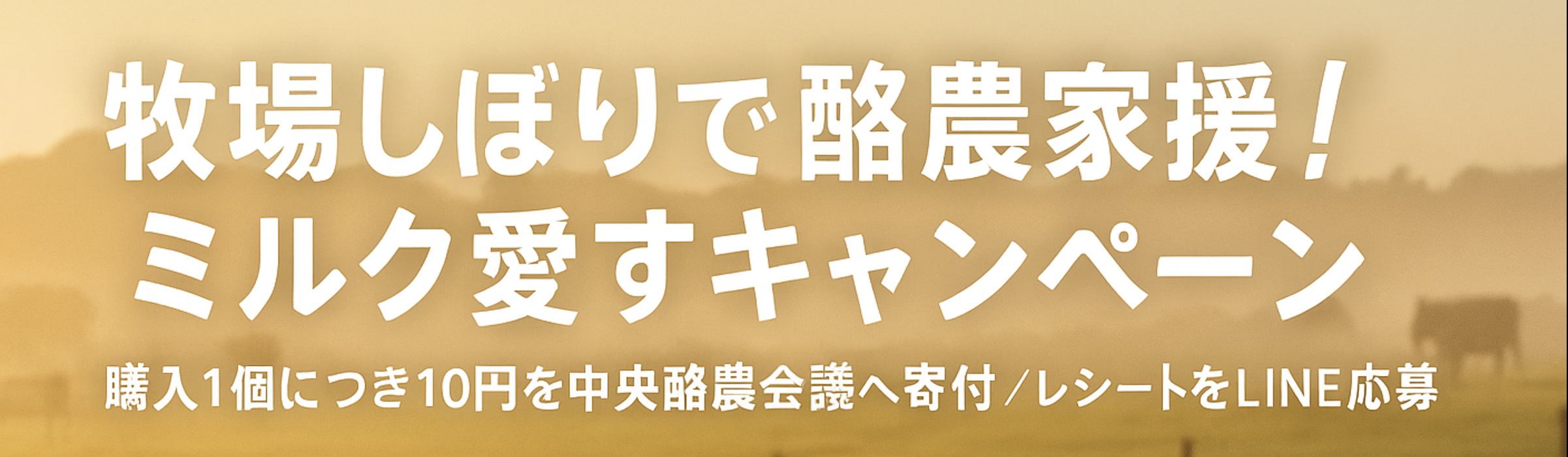

コメント