酪農家と米農家が協力して資源を循環させる「耕畜連携」の仕組みから、政府支援・成功事例、導入時の注意点(肝蛭リスク対策)まで、わかりやすく解説します。実践ノウハウ満載で飼料コスト削減&地域循環型農業を実現!

耕畜連携って?酪農と米農家のWin-Winな関係!
1. 耕畜連携とは?──基本のキホン
耕畜連携とは、
- **耕種農家(米農家など)**がつくる稲わらや籾殻を畜産農家(酪農家)が活用し、
- 畜産農家が生成する堆肥を田んぼに還元する、
というように“資源をぐるりと循環”させる農業モデルです。
特に注目されるのが、
- WCS(ホールクロップサイレージ):刈り取った稲を丸ごとサイレージ化した飼料
- 稲わら:粗飼料としての有効利用
- 籾殻:牛舎の敷料としての活用
これらを地域内で回すことで、廃棄物削減やコスト抑制、環境負荷低減を同時に実現します。

稲わら→牛のエサ→堆肥→田んぼへ!資源循環型のスマート農業!
2. 耕畜連携がもたらす3つのメリット
- 飼料コストの安定化・削減
- 輸入飼料に依存せず、地域内の資源で賄うことで価格変動リスクを低減
- 環境負荷の軽減
- 堆肥還元による化学肥料使用量の削減
- 廃棄されるわら・殻の再利用でCO₂排出抑制
- 地域循環型経済の促進
- 米農家と酪農家の新たな収入源創出
- 地域の耕作放棄地活用や雇用創出にも寄与

お米と牛が助け合う。農業って、こんなにあったかい!
3. 政府の支援政策と成功事例
- 飼料自給率目標:国内自給率を2020年の25%から2030年に34%へ引き上げ
- 畜産クラスター開発:飼料製造業者~酪農家~畜産センターを結ぶ地域連携支援
- 補助金・認証制度:飼料用米生産補助/エコフィード利用畜産物認証
広島県の事例
- 2000年頃からコミュニティ法人がWCS生産を開始
- 2011年に飼料特化品種「たちすずか」導入
- 2018年時点でWCS栽培面積562ha、うち「たちすずか」454ha
これらの取り組みが全国的にモデルケースとして注目されています。

国の目標にのることで、補助金や支援制度を活用しやすく!
4. 当牧場のリアルな取り組み紹介
当牧場では、地域の稲作農家と協力し――
- 稲WCS を乳牛のサイレージ飼料として給与
- 稲わら を肥育中の肉牛に粗飼料として活用
- 籾殻 を牛舎敷料に使用し、乳房炎予防や床替えコストを削減
さらに、家畜糞尿は自社堆肥として醗酵・熟成後に返還。
「双方向循環」を実現しています。

稲作×酪農のコラボで持続可能な畜産経営へ!

5. 稲わら導入時の注意点:「肝蛭リスク」とその対策
肝蛭(かんてつ)とは?
- 肝臓に寄生し、慢性肝障害を引き起こす寄生虫
- 稲わらに卵や幼虫が付着している可能性あり

稲わらにも寄生虫の卵が⁉肝蛭が潜んでいるかも…
リスクを抑える4つのポイント
- 出どころの確認
- 湛水期間や湿地帯の圃場はリスク大
- 受け入れ時の検査
- 糞便検査・血液検査で早期発見
- 乾燥・熱処理保管
- 十分な乾燥庫での保管や加熱処理で幼虫を死滅
- 農家との信頼構築
- どの田んぼで育った稲わらかを必ずヒアリング

稲わらは十分乾燥・保管!肝蛭リスクを事前にブロック
6. ステップ解説:はじめ方&ポイントまとめ
- パートナー農家を探す
- 地域のJA支部や農業公社に相談
- 契約・物々交換の仕組み作り
- 堆肥 ↔ 副産物(稲WCS・稲わら・籾殻)
- 品質管理体制の整備
- 受け入れマニュアル作成(肝蛭リスク対策含む)
- 効果測定・情報発信
- 飼料コスト、乳量・生育成績を定期的に数値化

まずはJAや農業公社に声をかけてみよう!
まとめ

次の一歩:まずは地域のJAや農業公社に相談し、小規模からトライ。効果を数値化しながら拡大していきましょう!
耕畜連携の基本:米農家の稲WCS・稲わら・籾殻と、酪農家の堆肥を地域内で循環させる仕組み。
主なメリット:飼料コストの安定化・削減、環境負荷の軽減、地域循環型経済の促進。
導入のポイント:パートナー農家の選定、品質管理マニュアル(肝蛭リスク対策など)の整備、効果測定と情報発信。
肝蛭リスク対策:出どころ確認・乾燥/熱処理・糞便検査・農家との信頼構築で安全性を確保。
今後の展望:大豆かす等の新副産物導入、地域ブランド化、オンライン発信によるノウハウ共有でさらに発展可能。

地域密着で耕畜連携を進める第一歩を!


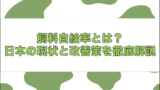
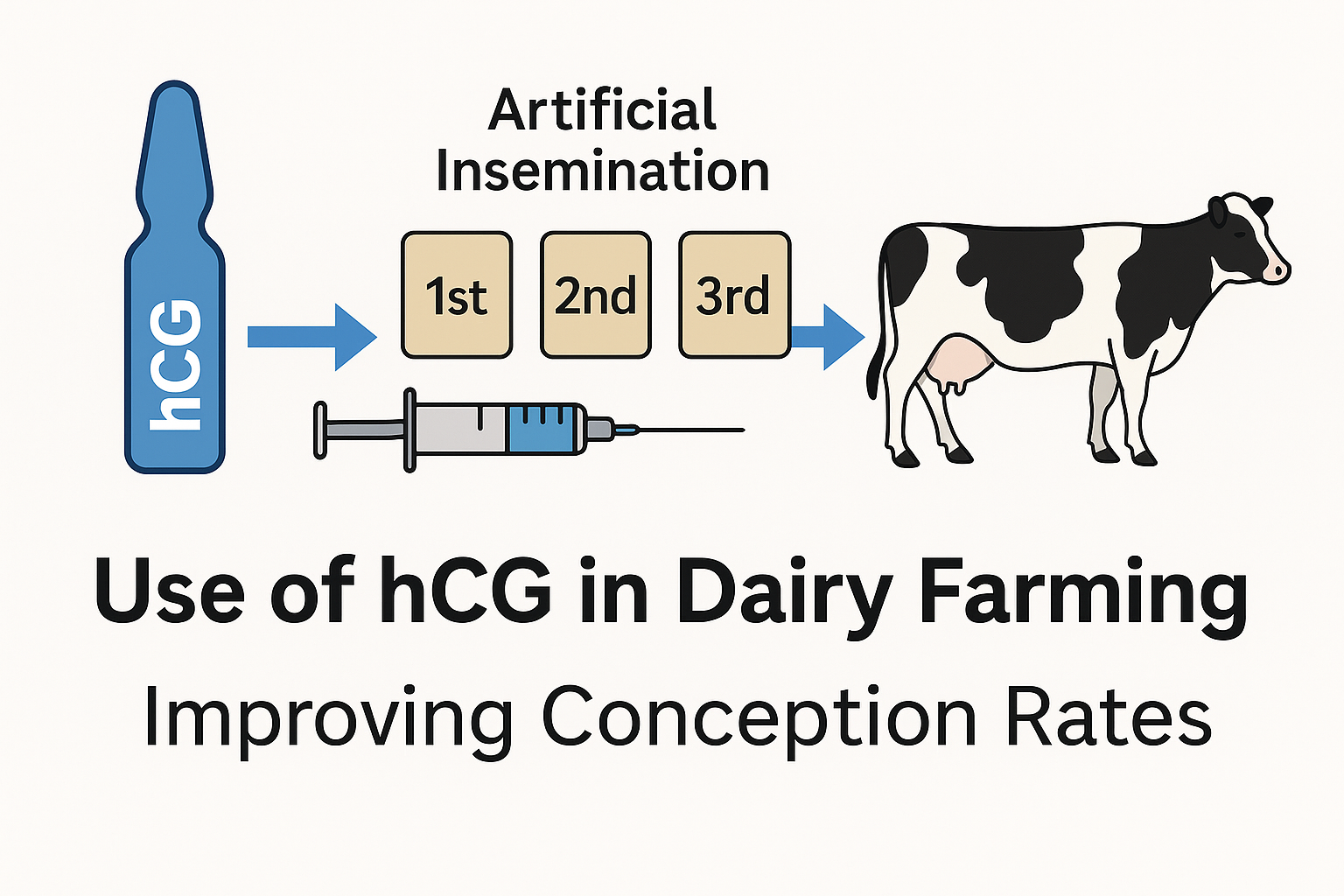
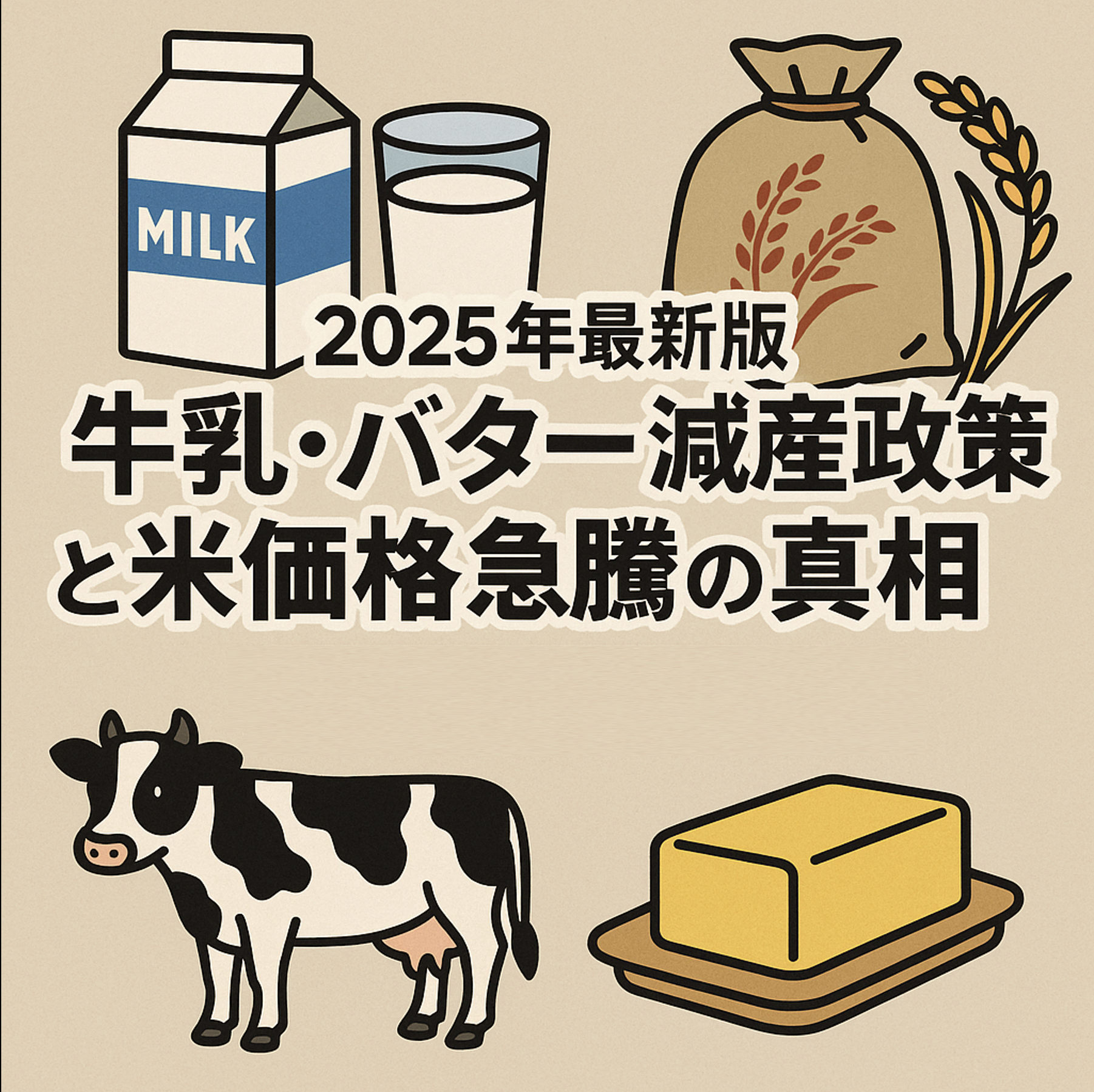
コメント