趾間フレグモーネ(趾間ふらん)は、乳牛や肉牛に発生する趾間の急性細菌感染症です。跛行や乳量低下、繁殖成績の悪化を招くため、早期発見と適切な対応が重要です。本記事では2級認定牛削蹄師である筆者が現場で使える実践的な対策を詳しく解説します。

乳量低下や繁殖不良を防ぐため、日常観察を徹底
1. 趾間フレグモーネの特徴
- 主因菌:Fusobacterium necrophorum(フソバクテリウム・ネクロフォーラム)。共力菌と混合感染することが多い。
- 発症部位:趾間隙(蹄の指の間)の皮膚・皮下組織。
- 臨床像:急性の強い跛行、趾間の腫脹・発赤、壊死や膿、場合によっては発熱や乳量低下。
- 誘因:湿潤で汚れた床面、小石や鋭利な物による皮膚損傷、過密やストレス。

趾間の腫れ・発赤・膿が見えたら感染の可能性

2. なぜ発生するのか?
趾間の皮膚は本来バリア機能がありますが、泥・糞・小石で擦れてできた微小損傷や蹄形不良があると、嫌気性菌が侵入して増殖します。F. necrophorumは毒素を産生し、局所壊死と強い炎症を引き起こします。湿潤環境は細菌増殖を助長します。

微小な皮膚損傷が感染の入り口!
3. 症状
早期発見がカギ。次のサインを見たら要注意です。
- 突然の片側あるいは両側の中等度〜重度の跛行(歩行時に足を引きずる)。
- 趾間の腫脹・発赤・熱感。
- 壊死や悪臭、膿の排出がある場合は進行例。
- 発熱、乾物摂取量(DMI)低下、乳量低下などの全身症状。
症状の重症度と経済影響
| 症状の重症度 | 特徴 | 経済的影響 |
|---|---|---|
| 軽度 | 局所腫脹、軽い跛行 | 乳量低下(短期) |
| 中度 | 壊死開始、発熱 | 治療費増加、繁殖遅延 |
| 重度 | 広範壊死、化膿 | 廃用リスク、損失大 |

早期発見で治療効果アップ!
4. 現場でできる応急処置
- 隔離・安静:清潔で乾いた個別スペースへ移動。
- 洗浄:温水で泥・糞を入念に洗い流す。刺激の強い消毒薬は避けるか獣医に相談。
- 壊死組織の除去:削蹄師や獣医が行う。壊死部は膿の温床になるため適切に除去。
- 蹄ブロック:健側にブロックを装着して患側を浮かせ、疼痛緩和と治癒促進。
- 記録する:発症日時・症状・処置内容を記録し、獣医へ報告。

清潔で乾いた場所に隔離・安静!

5. 獣医治療
標準治療は系統的抗菌薬の投与と局所処置、環境改善の併用です。代表的な薬剤や対処法は以下の通りですが、投薬は必ず獣医師の指示に従ってください。
- セフチオフル(ceftiofur):現場で広く用いられる抗菌薬。製剤ごとの添付文書に従うこと。
- オキシテトラサイクリン等の代替薬:状況・地域によって使用される場合がある。
- 局所処置:洗浄、壊死組織の除去、包帯やドレナージ、必要に応じた削蹄。
【重要】抗菌薬の選択・投与量・期間は獣医師の判断が必要です。薬剤耐性対策の観点からも自己判断での投薬は避けてください。

局所処置は洗浄・壊死除去・包帯で対応
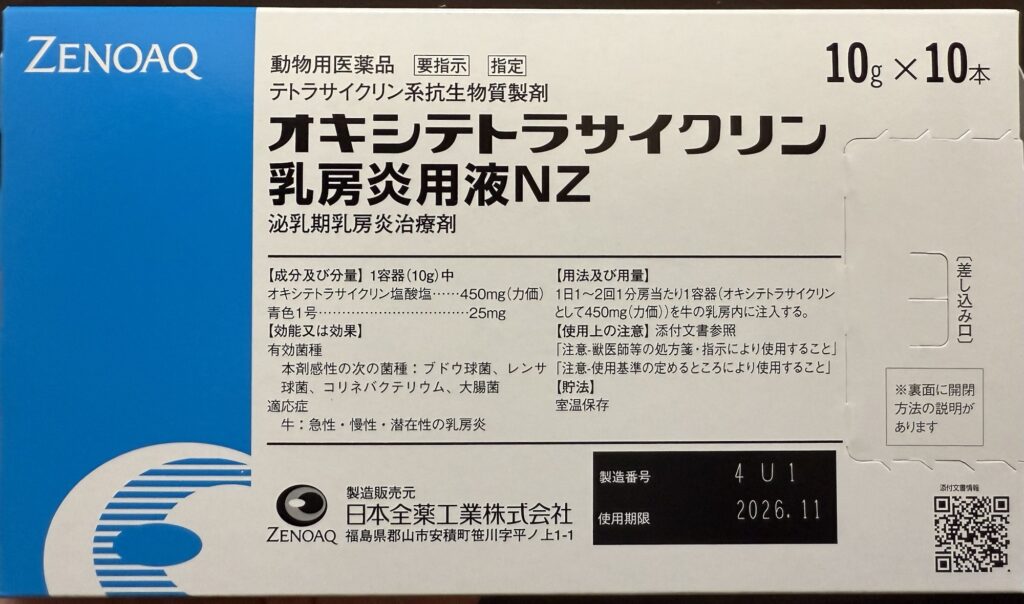
6. 予防対策
6.1 床面・環境管理(最優先)
排水改善や適切な敷料で床面を乾燥させ、泥や糞尿が滞留しないようにすることが最も効果的です。小石や鋭利な破片を除去して外傷リスクを下げてください。
6.2 定期削蹄・フットケア
年2〜3回の定期削蹄で蹄形を整え、荷重分布を改善します。蹄球びらんや蹄底潰瘍を同時に予防できます。
6.3 飼養管理・栄養
栄養バランスを整えることは蹄質改善につながります。特にビオチン補給は蹄の回復・強度維持に有益とされます。
6.4 導入牛の検疫と観察
導入牛は隔離して観察期間(少なくとも1〜2週間)を設け、蹄や皮膚のチェックを行ってください。環境変化やストレスが発症トリガーになることがあります。
6.5 モニタリングとスタッフ教育
日常点検ルーチン(歩様観察・趾間の目視)を作り、スタッフにチェックリストを配布します。早期発見が治療コストを下げます。

床は常に乾燥!泥・糞・小石を除去
7. よくある質問(FAQ)
Q:趾間フレグモーネは他の牛にうつりますか?
A:直接の飛沫感染ではないものの、汚染された床面や集約された通路など管理不良があると群内で多発することがあります。早期隔離が効果的です。
Q:自分で抗生物質を投与してもいい?
A:獣医師の診断と処方に従ってください。誤った投与は薬剤耐性や製品残留のリスクを高めます。
Q:再発しやすい牛には何をすべき?
A:蹄形や栄養、床面といった根本原因を検討します。個別の削蹄、栄養改善、環境改善で再発を抑制します。
8. 現場チェックリスト
- 毎日の歩様チェック(朝晩1回)
- 床面の乾燥・排水確認(週1回)
- 小石や破片の除去(必要時)
- 月次での蹄チェック+削蹄スケジュール確認(年2〜3回)
- 新規導入牛の隔離観察(最低1〜2週間)
- 異常発生時の獣医連絡先をスタッフ全員に周知
- 蹄浴(フットバス)の実施
9. まとめ
趾間フレグモーネは、早期発見・迅速な局所ケアと獣医の適切な抗菌治療、そして床面管理と定期削蹄による予防で多くを防げます。現場での小さな改善を積み重ねることが、牛の健康と経営の安定につながります。

床面管理で細菌繁殖リスクを低減
関連記事
酪農における蹄病と削蹄師の重要性
※本記事は一般的な知見をまとめたものです。具体的な治療・投薬は必ず獣医師の診断と指示に従ってください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

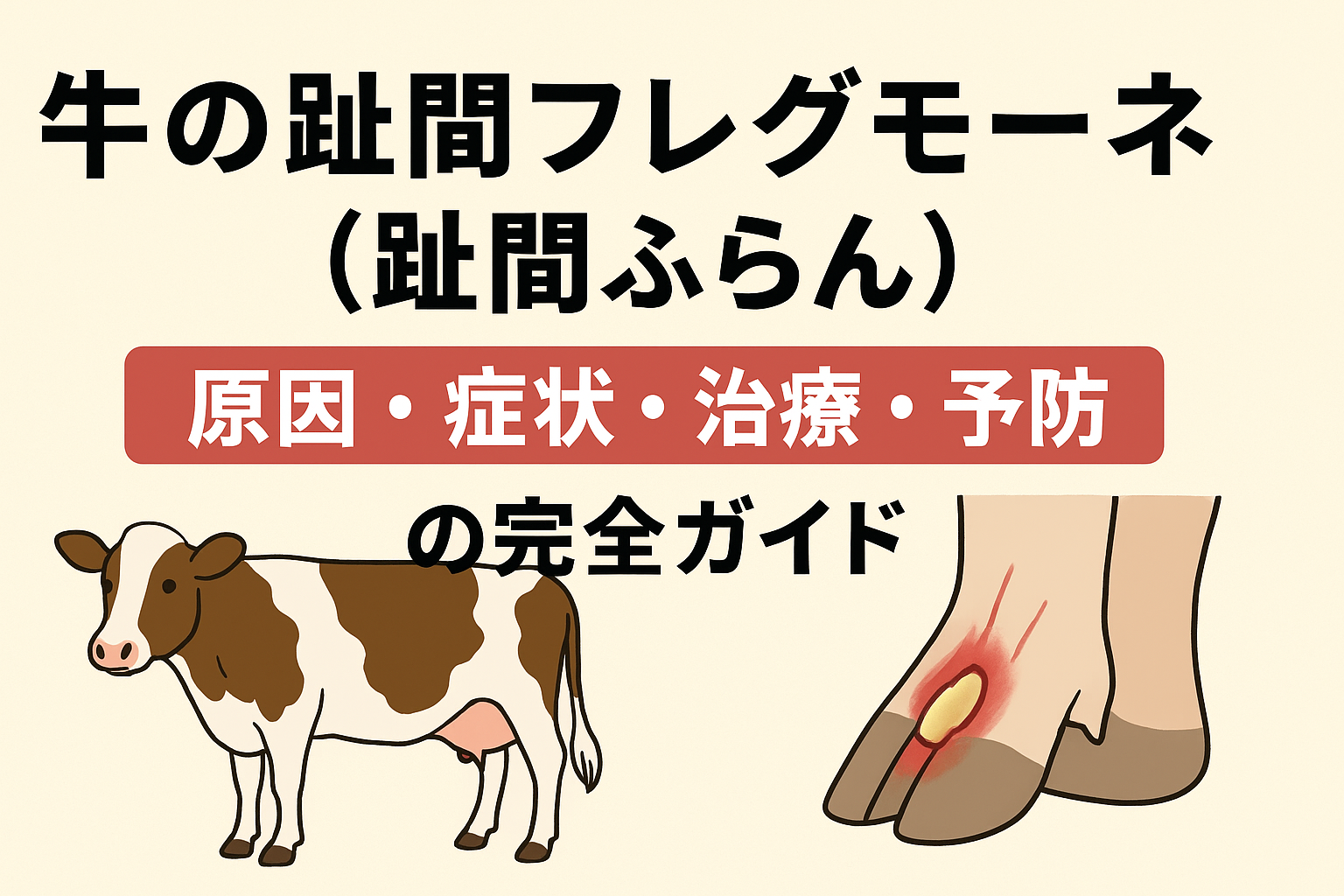

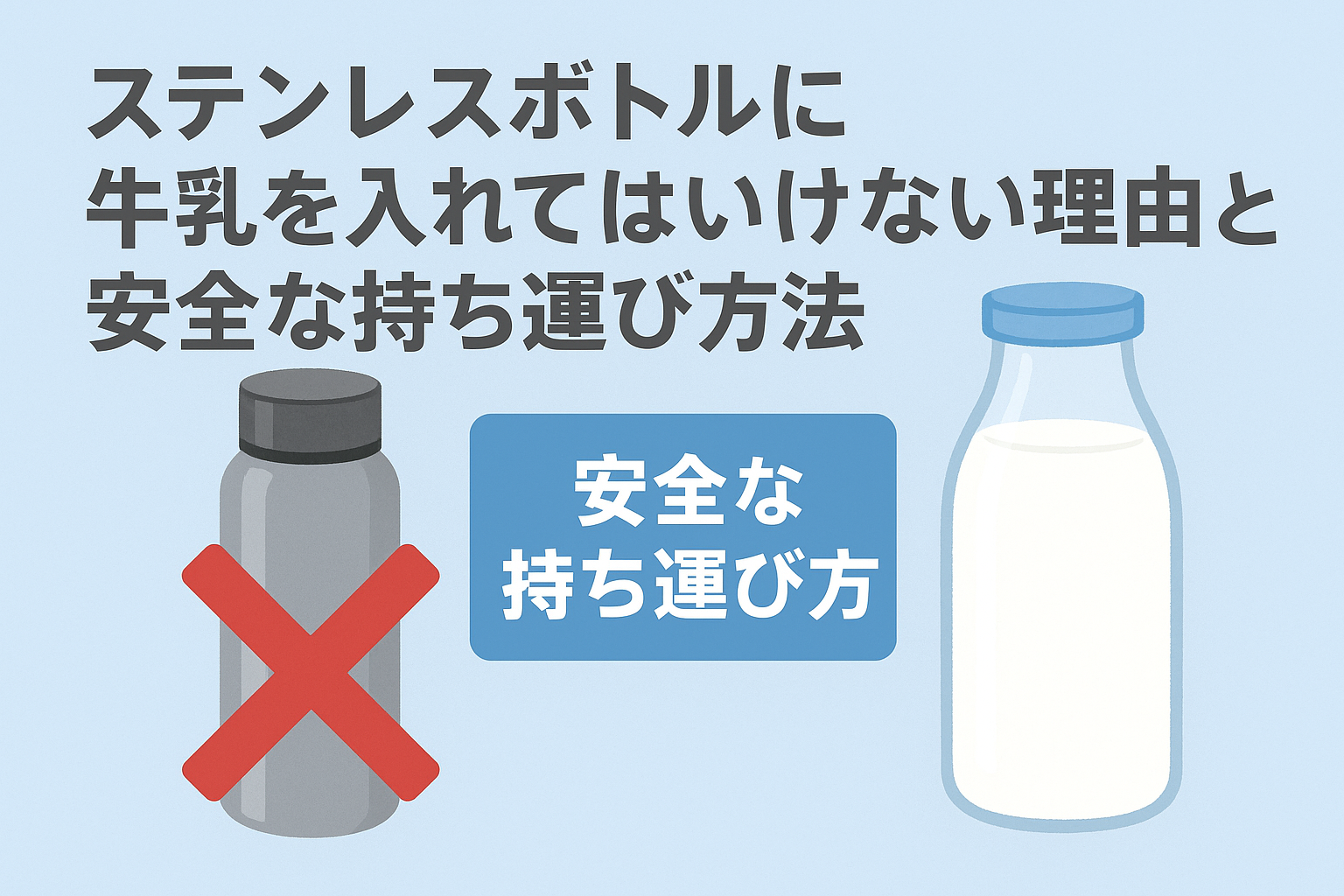
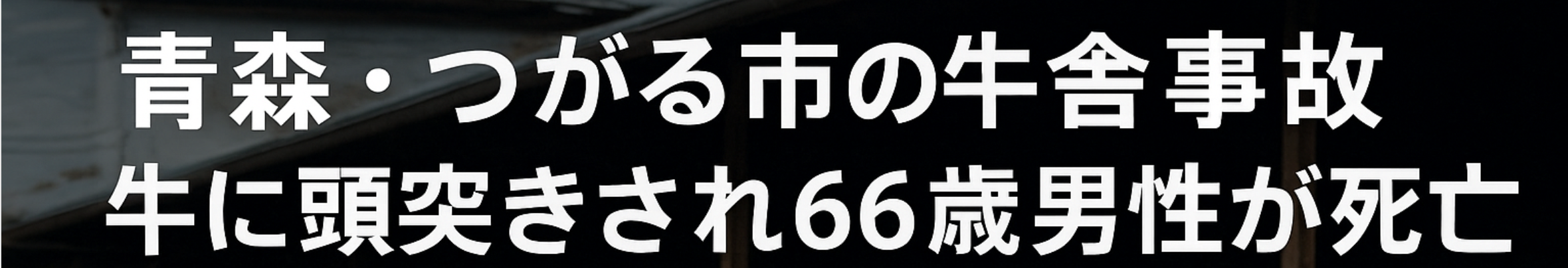
コメント