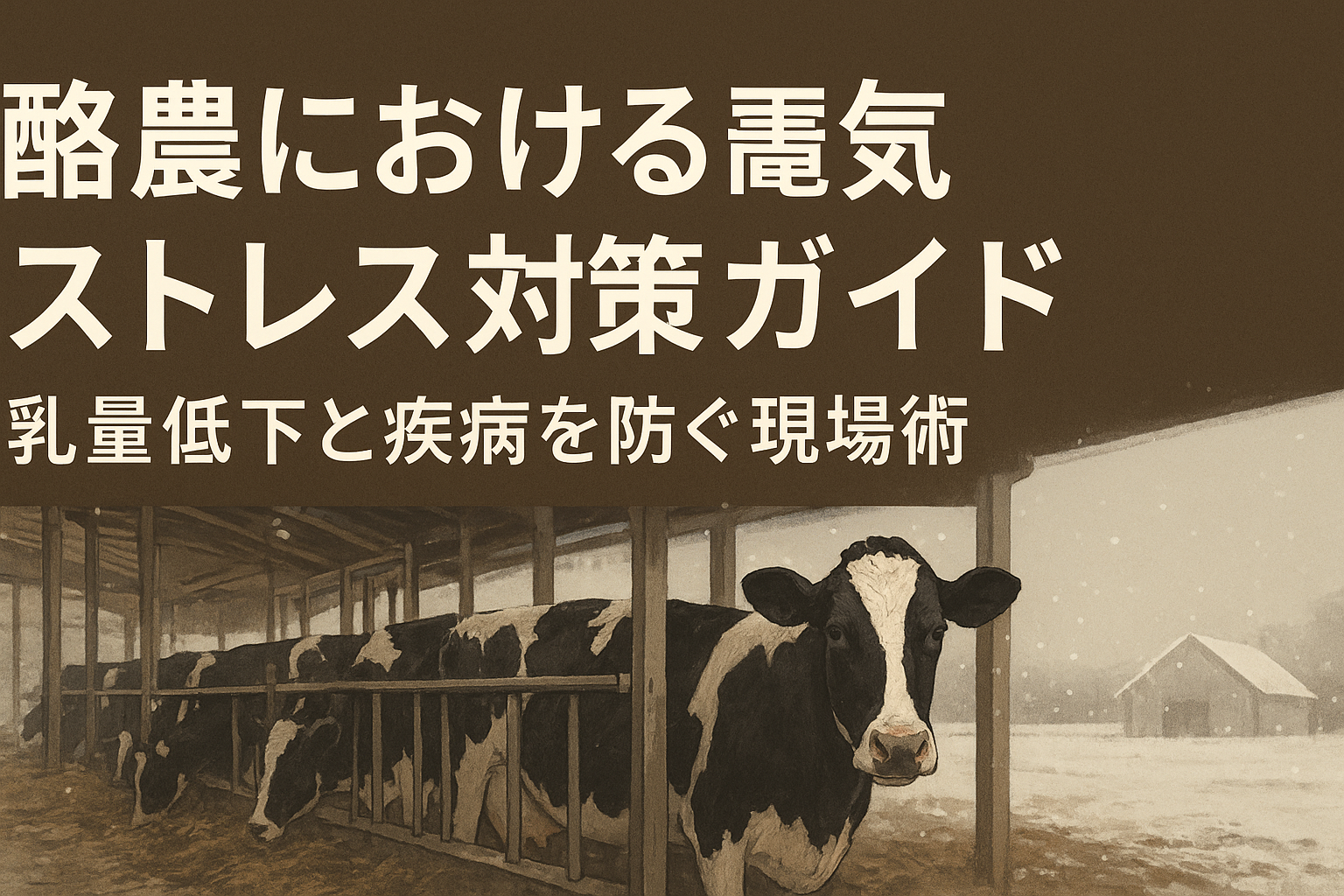学校給食で使われる牛乳ストローは、全国で大量に発生する廃プラスチックの一因です。本記事では、使用済みストローの回収フローから洗浄・粉砕・ペレット化、そしてベンチや文具などのアップサイクル事例まで、2025年時点の最新動向を踏まえて専門的に解説します。自治体・学校・企業が連携して実行できる導入チェックリストも掲載しているので、実務にそのまま使える実践的な内容です。
1. なぜ「学校給食ストロー」のリサイクルが重要か
学校給食で使われる牛乳ストローは、全国規模で見ると年間数千万本〜億本単位で発生する廃プラスチックの一部です。ストローレス化(直飲みパック導入)が進む一方で、既存在庫や特別なニーズでストローが残る現場も多く、回収・リサイクルを行うことで埋め立てや焼却を減らし、資源循環とCO2削減に寄与できます。

環境面と教育面の二重効果
回収活動は単に廃棄物を減らすだけでなく、児童が自らの行動で資源が生まれ変わる様子を学ぶ教育素材にもなります。班単位の回収コンテストや、再生品で作ったベンチを校庭に設置するなど、実体験を伴う学びが可能です。
2. ストロー回収から製品化まで:具体的な工程
- 分別・回収:使用後に洗浄しやすいように分別ステーションを設置。学校と地域回収拠点の協働が重要。
- 検品・洗浄:異物除去と洗浄で品質を確保。食品接触の可能性がある場合は十分な洗浄プロトコルを導入。
- 粉砕・乾燥:粉砕機で細断後、乾燥して含水率を下げる。
- 溶融・ペレット化:押出機で溶融し、ペレット状に。ここで再生プラスチックの均質化処理を行う。
- 成形・仕上げ:射出成形や圧縮成形でベンチ、プランター、文具、建材パーツ等を製造。
ポイントは「汚れ対策」と「用途に応じた品質管理」です。衛生面に配慮した工程設計と、強度や着色などの最終製品基準をあらかじめ決めておくことが成功の鍵です。
3. 代表的な事例(自治体・企業)
北九州市:地域回収→公園ベンチ化
政令市の先進事例として、地域の回収ルートとリサイクル工場を連携させ、回収したストローを再生プラスチックとしてベンチやプランターに加工。子どもたちの環境学習プログラムと連動させ、年間で数トン級の廃棄削減効果を報告しています。
江崎グリコ(企業):廃止とリサイクルのハイブリッドモデル
企業によるパッケージ転換(ストローレス移行)と、移行前のストローを回収して文具や包装材に活用する取り組みを実施。製造側の協力で回収後の流通がスムーズに回るモデルが構築されています。
高知県:パック回収とパルプ化の併用
ストロー廃止に伴い、牛乳パック本体の再利用(パルプ化)を推進。卒園証書や学用品への転用というユニークなアップサイクル例があり、自治体・学校双方にメリットがあります。
注:上記事例は2025年時点の取り組みを参考に整理したものです。導入状況は自治体・企業により異なります。
4. メリットと現場での課題
主なメリット
- 埋立・焼却削減による環境負荷低減(CO2削減効果)
- 資源循環による経済効果(再生材の付加価値)
- 児童の環境教育コンテンツとして活用可能
現場でよく挙がる課題
- 衛生管理:洗浄・乾燥工程の確保が必須。
- 回収率の確保:児童・教職員の協力を得る仕組み作りが必要。
- 代替ニーズ:障害のある児童などストローが必須のケースへの配慮。
- コスト:回収・前処理コストと製品化コストの均衡が課題。
5. 学校・自治体が導入する際のチェックリスト
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 回収フロー | 回収場所・頻度・保管方法の明確化(子どもでも分かる表示) |
| 衛生管理 | 洗浄プロトコル、乾燥設備、検品基準 |
| 連携先 | リサイクル業者、製品化事業者、自治体窓口の確保 |
| 費用負担 | 回収〜再生の費用分担(学校・自治体・企業の協力体制) |
| 教育プログラム | 学習教材の作成・体験学習の実施計画 |
導入前に上記を整理することで、運用コストやトラブルを事前に軽減できます。特に「回収の仕組み」は簡潔であるほど回収率が上がります。
6. よくある質問(FAQ)
Q1:回収したストローはどの程度きれいにする必要がありますか?
A:最終製品の用途によりますが、食品接触の可能性がある場合は徹底した洗浄と検品が必要です。一般的には目視で汚泥や異物を取り除いた後、温水洗浄→乾燥の工程を設けます。
Q2:全ての学校で導入可能ですか?
A:施設規模や予算により差はあります。小規模校では地域回収ステーションと連携するハブ&スポーク方式が有効です。
Q3:ストローレス化とリサイクル、どちらを優先すべきですか?
A:理想は両輪です。使用自体を減らす(ストローレス)ことが最も有効ですが、既存のストロー在庫や特別支援が必要なケースに対しては、回収→再生の取り組みが現実的な解決策になります。
7. まとめ:地域と学校で進める具体アクション
- 学校給食ストローは「削減(ストローレス)」と「回収→再生(アップサイクル)」の両戦略で対処するのが現実的。
- 回収工程は「分別→洗浄→粉砕→乾燥→ペレット化→成形」の流れが基本。衛生管理と品質基準が重要。
- 既存の成功事例(自治体、企業連携)は、教育プログラムとの連動が効果を高め、地域の支持を得やすい。
- 導入時は回収フロー、衛生プロトコル、連携先、費用負担、教育プログラムの5点をチェックリスト化しておくと運用が安定する。
- 小さな試行から始め、成果を見せてスケールアップする「段階的導入」が現場で成功しやすい。
学校給食の使用済みストローのリサイクルは、単なるゴミ削減策ではなく、資源循環を学ぶ教育のプラットフォームにもなります。まずは小さな回収プロジェクトから始め、効果が確認できた段階で自治体や企業と連携しスケールアップを図るのが現実的です。
具体的には:
- 分別ボックスの設置・回収ルールの明確化
- 近隣のリサイクル事業者への協力要請
- 学習プログラムと連動した回収イベントの開催
これらを実施することで、地域の可視化された成果(例:再生ベンチの設置)が生まれ、保護者や地域からの支持を得やすくなります。
関連記事
給食に牛乳が出る理由とは?栄養面から考える牛乳の重要性
掲載日:2025年10月9日
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。