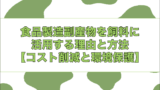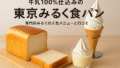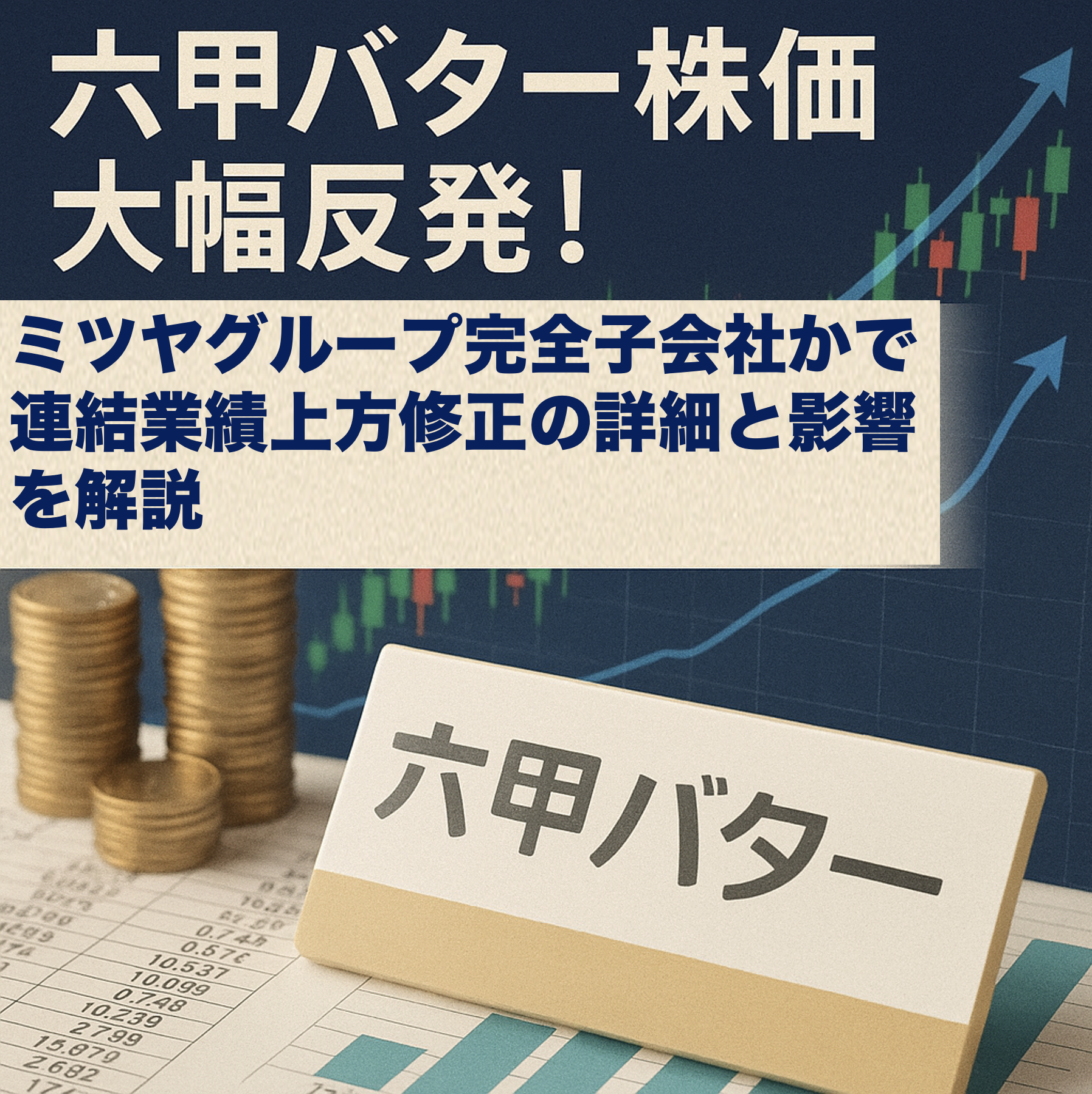スターバックスをはじめ、多くのカフェで毎日大量に発生する「コーヒー粕(SCG: Spent Coffee Grounds)」。これを廃棄せず、牛の飼料として活用する循環型酪農が注目を集めています。本記事では、コーヒーかす飼料のメリット・注意点から、実際の処理方法、環境への貢献までをわかりやすく解説します。

スタバの“コーヒーかす”が牛のエサに!?サステナブルな取り組みが進化中
コーヒーかすを“資源”に変える理由
- 大量廃棄の課題:日本の都市部では、年間数千トンのコーヒーかすが発生。埋立処分ではメタンなど温室効果ガスを生み、環境負荷が問題に。
- 循環型経済の実践:「廃棄→消費」ではなく「消費→再資源化→再利用」というクローズド・ループを構築し、廃棄物を“資源”に変える。
- 地域資源の活用:大豆をはじめとする輸入飼料の使用量を減らし、地元で出る副産物を有効活用することで、コスト削減と地産地消費を両立。

牛のエサにコーヒー!?都市のゴミが酪農を支える時代に
循環型供給網の実現
スターバックスの供給網を循環型にすることを目指しています。具体的には、以下の流れでクローズド・ループが構築されています。
- コーヒー豆が店舗で使用され、コーヒーかすが発生。
- コーヒーかすが収集され、メニコンの発酵技術で牛の飼料に変換。
- この飼料を食べた牛から高品質な牛乳が生産。
- 生産された牛乳がスターバックスの店舗でドリンクに使用。
成果
日本では、一部の店舗でこの牛乳が実際に使用されており、2014年以降、継続的に実施されています。2022年には、スターバックスが「コーヒーかす循環」をテーマにした新しい店舗をオープンし、この取り組みをさらに推進しています(Starbucks Japan opens new store focused on coffee grounds circularity)。
コーヒーかすの栄養価と混合割合のポイント
基本的な栄養成分
- 乾物率:約91.1%
- たんぱく質:11.8%
- 脂 質:23.1%
- 繊維質:42.5%
- カフェイン:0.13%程度
高繊維・中脂質の特性を持ち、エネルギー源というよりは「かさ増し」としての役割が大きいです。

意外と高たんぱく!酪農飼料の一助として注目
混合割合と健康への影響
- 5~10%:
- 乳量や乳脂肪率にほとんど影響なし
- メタン排出を約20%削減
- 10%超:
- 消化率の低下リスク
- 過剰なカフェイン摂取によるストレスや泌尿器刺激の可能性
→ ポイント:はじめは5%程度から試し、牛の体調や消化状態を観察しながら徐々に調整しましょう。

メタン排出20%削減!地球にも牛にもやさしい飼料
堆肥としての活用ポイント
特性と効果
- 窒素約2%、微量のリン・カリウムを含む有機物
- 土壌改良:水分保持・通気性・排水性を改善
- 高温維持:25%配合で57~68℃を2週間以上維持 → 病原体・雑草種子抑制
- 害虫忌避:ナメクジ・ダンゴムシを遠ざける効果

害虫よけ効果アリ!?ナメクジが寄りつかない!
主な活用方法
| 方法 | 特徴 | ポイント |
|---|---|---|
| 直接混ぜ込む | 少量を土にまき、混ぜて覆う | 窒素一時減少に備え追肥を検討 |
| 堆肥堆/回転式堆肥器 | 緑材料として他の材料と1/3以下で混合、定期攪拌 | 緑(コーヒーかす)と茶(落ち葉等)のバランス |
| ボカシ堆肥化 | 1~2日ごとに麹を添加、4~6週間で完成 | スペース節約・早期発酵 |
| ワームコンポスト | ミミズが好むためフィルターごと投入、キャスティング生成 | 初回は少量から、ミミズの様子を確認 |
注意点
- **過剰使用(総量15~20%超)**で土壌酸性化・圧密化の恐れ
- 発酵過程で窒素を一時的に消費 → 必要に応じて窒素肥料を追加
- 一部植物は生かすと阻害リスクあり → 事前の堆肥化推奨

発酵中は窒素が減るから追肥でバランス調整を
処理方法──安全に、効率よく
- 回収・分離
- 店舗から発生するコーヒーかすを専用の容器で回収。
- 異物(プラスチックフィルターなど)が混入しないよう、手作業で取り除く。
- 前処理(発酵/乾燥)
- 発酵処理:乳酸菌(ラクトバチルスなど)を用い、悪臭を抑えつつ保存性を高める。
- 乾燥処理:フラッシュ乾燥やペレット化機器を使い、長期保存と飼料混合時の扱いやすさを両立。
- 混合・給餌
- 完全乾燥後、他の粗飼料(牧草、豆粕など)と均一に混合。
- 毎日同じ時間帯に給餌し、牛の採食量と消化状況を記録。
- モニタリング
- 乳量・体重・健康状態を定期チェック。
- 問題があればすぐに混合割合を見直す。

異変はすぐに混合割合を調整、牛の健康を守る!
環境への具体的効果
- メタン排出量の削減:反芻動物の腸内発酵プロセスを変化させ、メタン生成を約20%抑制。
- 廃棄物削減:埋立処分ゼロに近づき、埋立地の延命化にも貢献。
- 輸入飼料代替:大豆粕の一部代替で輸送コスト・カーボンフットプリントを低減。
これらは気候変動対策やSDGsにも直結する取り組みです。特に都市部から近い酪農場では、回収輸送距離が短いため、さらに効果的に導入できます。

SDGs推進に直結する循環型酪農
飼料以外の活用アイデア
- 牛舎床材:発酵コーヒーかすを敷くことで、悪臭軽減や床面のクッション性向上に寄与。
- 堆肥化:発酵済みかすを堆肥に混ぜ、畑作や野菜栽培に利用。
- バイオマス燃料:乾燥させたコーヒーかすを固形燃料として発電や暖房に活用する実証実験も進行中。
酪農と併せて多角的に活用することで、さらなる付加価値を生み出せます。

牛舎の床材に使えば悪臭軽減&クッション性アップ!
実際に東京都八王子市にある磯沼牧場ではフリーバーンの牛舎にコーヒー粕を使用しています!

導入する農家さんへ
- 小規模からスタート:最初は少量(5%程度)で混合し、牛の健康や乳質への影響を確認。
- 専門家と連携:発酵技術や栄養バランスの調整は、大学やリサイクル業者と共同で行うと安心。
- データ記録を徹底:乳量、体重、採食量、糞便状態などを毎日記録し、変化を見逃さない。
- 地域ネットワークを活用:近隣カフェやコーヒーショップと提携し、安定した回収ルートを構築。

毎日のデータ記録が成功のカギ!乳量や体調を見逃さない
まとめ:コーヒーかすが切り開く循環型酪農の未来
- 5~10%混合で乳量・乳脂肪にほとんど影響なく、安全に使用可能。
- メタン排出を約20%削減し、気候変動対策にも貢献。
- 前処理(回収→発酵→乾燥)を徹底し、異物除去や品質管理を実施。
- 専門家や地域ネットワークと連携し、小規模からモニタリングしながら導入を。
- 廃棄物削減と地産地消費を両立し、持続可能な酪農のモデルケースに。
- 堆肥活用:土壌改良・病原体抑制・害虫忌避など多彩なメリット。
コーヒーかすを牛の飼料として再利用する取り組みは、環境負荷の軽減だけでなく、酪農の新たな付加価値や地域資源の有効活用を促進します。適切な前処理と混合管理を行えば、5~10%の範囲で安全に使用でき、メタン排出削減や輸入飼料代替といった効果も期待できます。まず小規模から導入し、専門家・地域ネットワークと協力しながら実践してみてください。持続可能な酪農への一歩として、コーヒーかすをぜひ“宝の山”に変えていきましょう!

コーヒーかすは酪農の“宝の山”!新しい付加価値と地域活性化に
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。