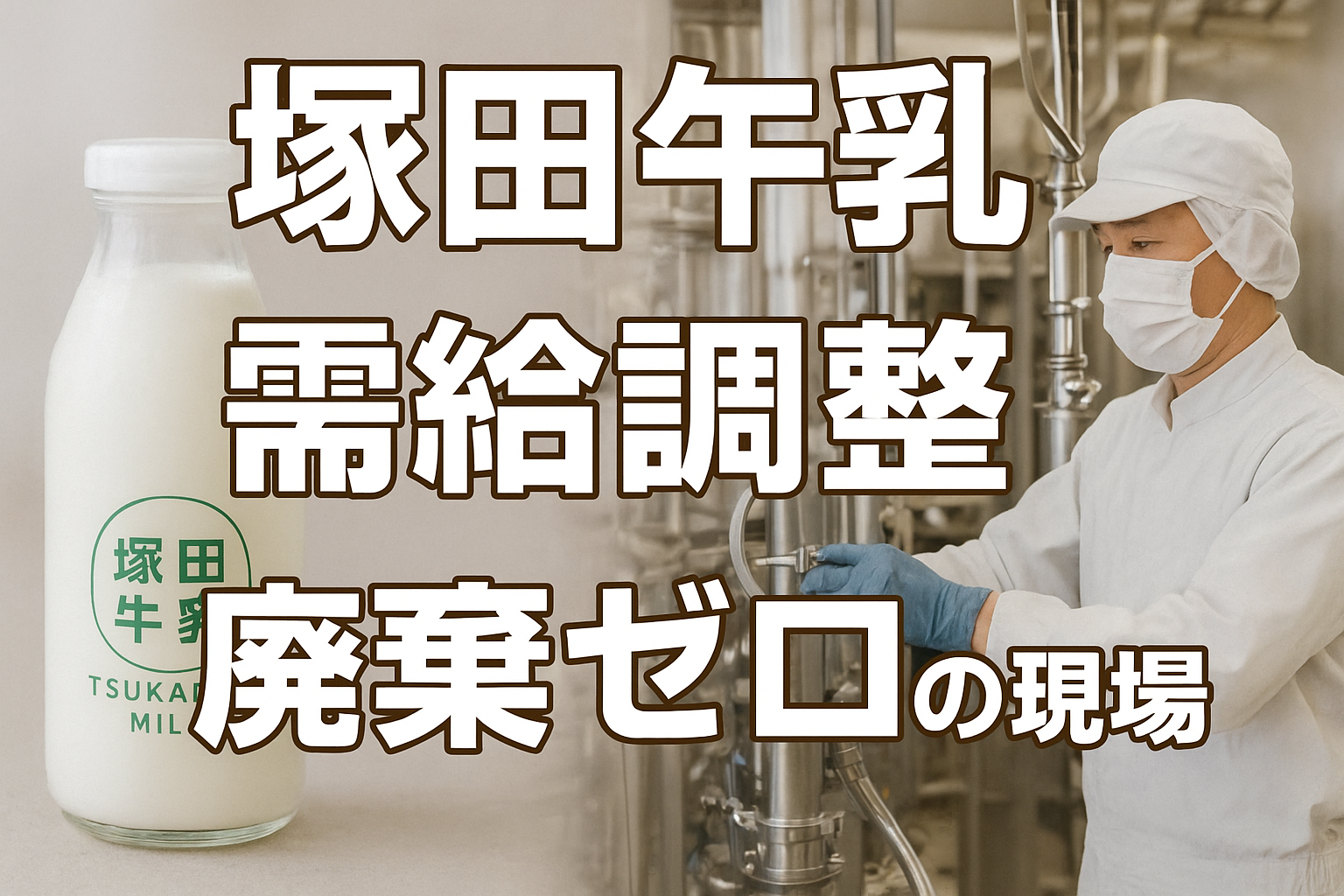新潟の老舗・塚田牛乳(創業1901年)は、学校給食供給や瓶牛乳の再提案、加工転用による“廃棄ゼロ”の仕組みづくりで、地域の牛乳需要を支え続けています。本記事では現場の数値と事例をもとに、需給調整の具体手法と需要拡大策をわかりやすく解説します。
塚田牛乳の概要:伝統と地域密着の経営
塚田牛乳(株式会社塚田牛乳)は1901年創業の新潟の老舗乳業で、2025年時点で創業124年を迎えています。新潟市江南区を拠点に、学校給食用牛乳や宅配、地元店舗向けの瓶牛乳・加工品(バター、練乳等)を製造。5代目社長の塚田忠幸氏の下、SNS発信や地域コラボを活用した商品開発で若年層へのリーチも強化しています。
主な数値(現場の指標)
- 学校給食向け供給比率:飲用生乳の約10%を占める
- 充填能力:毎日約42,000本、最大で1時間に7,000本を充填可能
- 容器比率:紙パックと瓶でおおむね7:3(用途に応じて使い分け)
需要拡大への具体的施策
国内の牛乳消費が長期的に低迷するなか、塚田牛乳は複数の角度から需要喚起を図っています。以下は主な取り組みです。
1. 学校給食の安定供給と子ども向けブランディング
学校給食向けの安定供給は地域での基盤需要を支える重要戦略。子どもたちに地元の牛乳を味わってもらうことで「塚田育ち」というブランド認知を醸成し、将来的な消費習慣の維持につなげています。
2. 瓶牛乳の再提案と環境価値の訴求
環境配慮の観点からガラス瓶を推進することで付加価値の創出。地元カフェやレストランとのコラボで瓶牛乳の体験価値を高め、若年層の消費を引き出す施策が奏功しています。
3. SNSと地域コラボによる話題化
公式のSNSで新デザインや限定コラボ商品を発信。投稿からの導線で購入ページや工場見学の情報へ誘導し、ブランド接触の機会を増やしています。
生乳の需給調整:現場で実践する“廃棄ゼロ”の仕組み
生乳は搾乳のタイミングが固定されるため、需給バランスが崩れた際の対応が不可欠です。塚田牛乳で実践されている手法を解説します。
加工転用で余剰を吸収
学校の長期休業や季節的な消費低下時には、生乳をバター・脱脂粉乳・練乳といった保存可能な加工品へと転用します。計画的な加工作業と在庫管理により、廃棄を最小限に抑える運用が可能です。
衛生管理と工場稼働の最適化
受け入れから出荷までの衛生管理体制を厳格に運用し、工場の稼働率を調整することで季節波動に対応。品質を確保しつつ柔軟に生産計画を変動させる運用ノウハウが重要です。
実務ポイント:加工ラインの稼働切り替え(飲用→加工)を短時間で行える工程設計と、加工品の販売チャネル(業務用・通販)を確保しておくことがカギになります。
品質問題と透明性:回収対応から学ぶこと
企業としての透明性はブランド信頼に直結します。塚田牛乳は公表された回収事案(2025年6月の一部商品の回収など)に対して速やかに告知し、対応を実施しました。重要なのは単なる告知にとどまらず、再発防止策や検査体制の強化を具体的に示すことです。
信頼回復のポイント
- 回収理由と範囲の明示、消費者が取るべき行動の明確化
- 再発防止のための工程改善(検査頻度・外部委託検査の導入など)
- 第三者機関による検証結果の公表(可能な範囲で)
FAQ(よくある質問)
Q1:学校給食に使われている塚田牛乳は安全ですか?
A:受け入れから出荷までの衛生管理を徹底しており、学校給食向けの充填工程は別ラインや専用基準で運用されています。
Q2:瓶牛乳と紙パック、どちらを選べばいいですか?
A:味覚や環境配慮の観点で選択が変わります。瓶は風味保持とリユース性が高く、紙パックは保存・携帯に便利です。
Q3:廃棄が心配な時期はありますか?
A:需要が大きく落ちる長期休校期などでは加工転用で余剰を吸収する運用を行っています。
まとめ:地域とともに育てる“持続可能な牛乳”
- 塚田牛乳は創業124年の地域密着型乳業で、学校給食や瓶牛乳で基盤需要を確保。
- 生乳需給の乱れは加工転用(バター・練乳・脱脂粉乳等)で吸収し、廃棄を抑制。
- 回収事案への迅速な公表と、再発防止の工程改善・検査強化が信頼回復の要。
- SNSや地元コラボで若年層への訴求を行い、瓶牛乳の体験価値を高めて需要拡大を図る。
塚田牛乳は「伝統」と「現場力」を武器に、学校給食や瓶牛乳の提案、加工転用による需給調整など複合的な施策で地域の牛乳需要を支えています。品質管理・透明性の徹底と、消費者に届く体験価値の提供が、今後の成長の鍵です。
地域ブランドとしての強さを活かしながら、あなたも日常で「地元の牛乳」を試してみてください。新しい発見があるはずです。
参考:企業公表情報、地域メディアインタビュー、工場公表データなど(詳細は公式情報をご確認ください)。
※本記事の数値や記述は公表されている情報と現場の整理に基づいています。公開後の変更がある場合は公式発表を優先してください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。