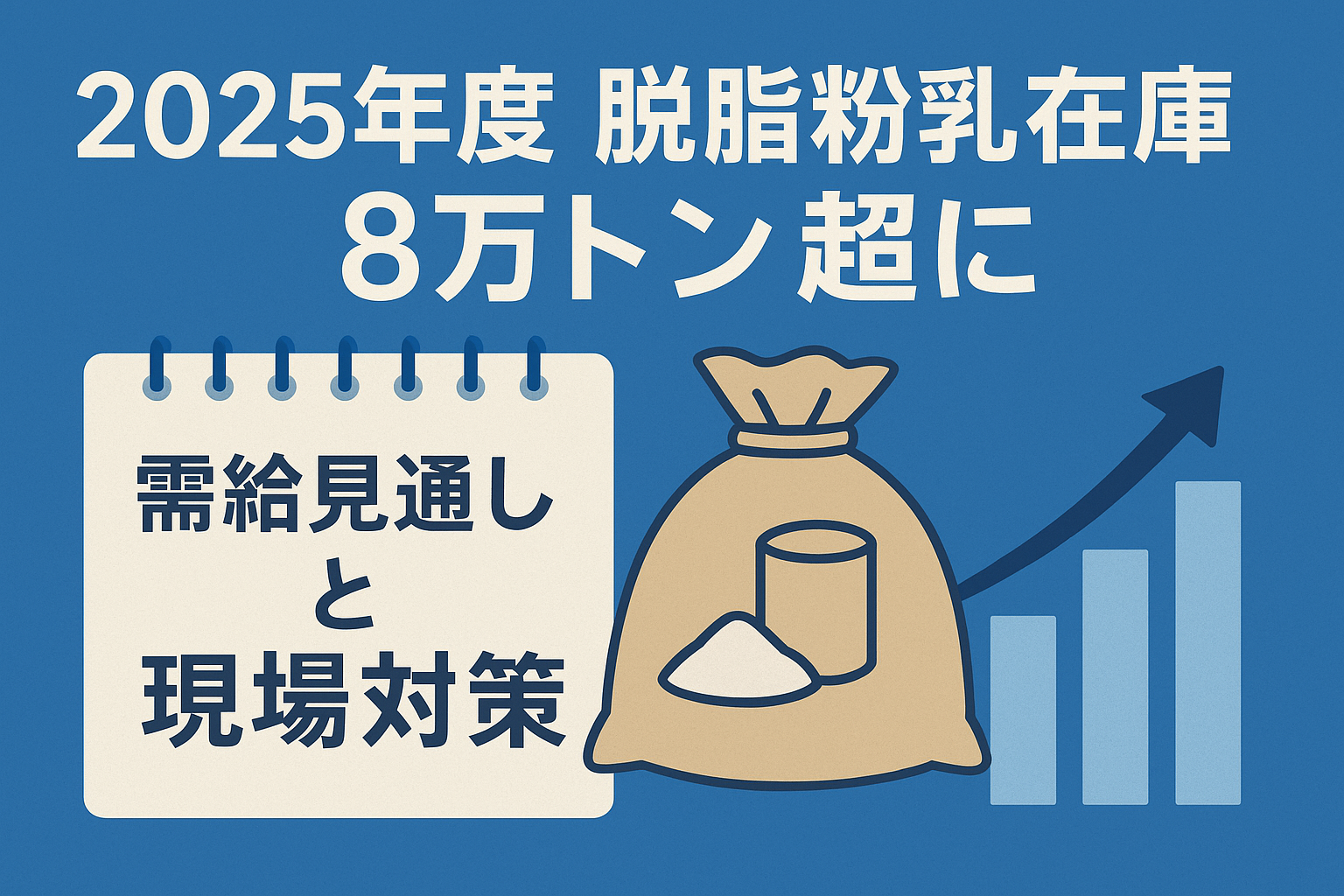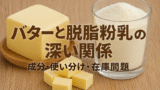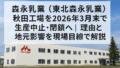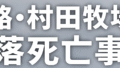2025年度、脱脂粉乳(脱粉)の期末在庫が約8.06万トンに達すると予測され、業界で大きな注目を集めています。乳価上昇に伴う消費減と北海道の生乳増産が重なった結果であり、酪農経営や加工・流通に具体的な影響が出始めています。本記事では主要数値を押さえつつ、現場で実行できる短期〜中期の対策を現場目線で整理します。
1. 予測の概要 — 主要データ
Jミルクの2025年度需給見通し(製品換算ベース)を要約すると、脱脂粉乳の主要数値は以下の通りです。この記事では現場で使える形で要点を整理します。
| 項目 | 2025年度見通し(製品換算) | 備考 |
|---|---|---|
| 脱脂粉乳 生産量 | 156,300 トン(15万6,300トン) | 前年比 約101.2% |
| 脱脂粉乳 出回り量 | 128,400 トン(12万8,400トン) | 在庫積み増しを除外した比較での考察あり |
| 脱脂粉乳 期末在庫(見通し) | 80,600 トン(8万600トン) | 前年比 約155%、在庫月数 7.5か月 |
| 単年度ギャップ(在庫積み増し要因) | 約28,600 トン | 生産 > 出回りの差分 |
| 2024年度末 在庫 | 52,000 トン(5万2,000トン) | 在庫月数 約4か月 |
※ 上記数値は需給見通しの製品換算を基に整理しています。数値は年度通期の見通しであり、四半期推移や加工計画で変動する可能性があります。
2. なぜ在庫が増えるのか(背景要因)
1) 乳価上昇による消費減
乳価の上昇は小売価格に波及し、飲用牛乳や乳飲料の消費量に顕著な下押し圧力を与えています。飲用向けの出回り量が落ち込む一方で、生乳の供給は一定の基準で維持されるため、加工向け(とくに脱脂粉乳)への回流が増えて在庫が積み上がる構図が生まれます。
2) 北海道での増産シフト
全国の生乳は2年ぶりの減産予測である一方、北海道は増産に転じています。北海道の生乳は加工原料にまわりやすく、脱脂粉乳やバター向けの加工が増えると、短期的には脱脂粉乳在庫の増加につながります。
3) 流通と非系統流通の影響
非系統(自主流通)での取引量や加工スケジュールの調整が難しい場合、需給調整のタイミングが合わず、一部が在庫に残ることがあります。加工場の稼働方針や輸送条件も在庫動向に影響します。
3. 酪農現場・市場への影響
価格面のリスク
在庫過多は原料需給に上向きの圧力をかけ、結果的に脱脂粉乳の市場価格低下→連動して生乳価格の抑制要因になる可能性があります。酪農家の収入が下押しされる局面に注意が必要です。
加工業者・流通への影響
脱脂粉乳の在庫が長期化すると、加工ラインの稼働計画見直し(生産シフト、ライン停止)を迫られることがあります。特にバターと脱脂粉乳の需給バランスが崩れると、メーカーの生産戦略にも影響します。
現場での実務的影響(経営面)
- 出荷価格の下落リスク→収益性の低化
- 代替加工先の交渉力低下(需要側が在庫を抱えると、買い控えが起きやすい)
- 季節変動時の在庫調整コスト増
4. 現場で取れる具体的対策(短期・中期)
短期(今季〜数か月)
- 販売先の多様化:業務用(製菓・製パン)や給食、食品メーカーへの直接販路を探る。脱脂粉乳は用途が広いので、用途提案で動きを作れる。
- 共同出荷・共同販売:複数農家でロットをまとめて販売促進を行い、交渉力を高める。
- 一時的な加工転換:生乳を脱脂粉乳以外の製品(クリーム・チーズ向け等)に割り振れるか検討する。工場の受け入れキャパにより難易度は異なるが、メーカーと協議の余地あり。
中期(半年〜2年)
- 付加価値商品の開発:高付加価値の乳製品(発酵食品や地域ブランド品)を共同で作ることで過剰在庫リスクを下げる。
- 在庫活用の多角化:脱脂粉乳を原料とした飼料や工業用途への転用、輸出ルートの開拓を検討する(規格・検査対応が前提)。
- 需給見える化の強化:生産計画と加工需要の共有プラットフォームを地域で作り、在庫積み上げを予防する。
現場からのチェックリスト(実務)
- 出荷先の月別需要見込みを作る(3〜6か月先)
- 加工先と月次の受入れ調整を契約で明確化
- 余剰生乳の代替用途(飼料、地元加工品)を事前に確保
5. 政策/業界の動きと期待される支援
需給調整に向け、業界団体や関係機関は基金や在庫調整事業を実施しています。短期的な在庫圧縮のための資金支援、及び中長期の生産調整策・消費喚起策が重要です。政策面では輸入枠の見直しや業務用需要喚起策などが議論の対象になります。
※ 現場の立場としては、支援資金を活用した短期的なキャッシュフロー支援と、中長期では製品多角化のための技術支援が特に有効だと考えます。
6. まとめ(今後の注視点)
- 主要数値:脱脂粉乳の期末在庫は約80,600トン(在庫月数約7.5か月)に拡大見込み。生産は増加、出回りは相対的に鈍化。
- 原因:乳価上昇による飲用牛乳の消費減と、北海道での生乳増産が在庫積み上げを促進。非系統流通や加工スケジュールのズレも要因。
- 影響:在庫過多は脱脂粉乳価格の下落圧力→生乳価格抑制→酪農家の収入圧迫につながるリスクが高い。加工・流通側も稼働調整を迫られる可能性あり。
- 現場でできる対策:短期は販路の多様化(業務用・給食等)、共同出荷、加工転換の交渉。中期は付加価値商品の開発、在庫活用の多角化(飼料・工業用途・輸出検討)、地域での需給見える化。
- 政策・支援の役割:短期的な資金支援(在庫調整基金等)と中長期の生産調整・消費喚起策が重要。現場は支援制度を積極活用しつつ自助努力で販路確保を進める必要あり。
2025年度の脱脂粉乳期末在庫は約8万トン超と大幅に積み上がる見込みで、これは酪農業界にとって無視できないシグナルです。背景には乳価上昇による消費減と北海道での増産があります。現場では短期的な販路多様化や共同販売、中期的な製品転換・付加価値化が鍵になります。
現場からの提案は次の3点です:
- まず「販路の横展開」を即実行する(業務用・給食等の需要獲得)
- 地域で「在庫見える化」を進め、加工と生産のズレを早期に察知する
- 業界団体の支援制度を積極的に活用し、短期的な資金繰りを安定させる
在庫問題は一朝一夕で解決するものではありませんが、現場でできる手を早く打つことでダメージを最小化できます。この記事が、現場で取れる具体策を考えるきっかけになれば幸いです。
FAQ(よくある質問)
脱脂粉乳の在庫月数とは何ですか?
在庫月数は「期末在庫 ÷ 月平均出回り量」で算出されます。在庫月数が長いほど、在庫が滞留している状態です。
在庫が多いのにバターが不足するのはなぜ?
脱脂粉乳とバターは製造プロセスで同時に出る副産物関係にありますが、それぞれ用途や需要の季節性が異なります。脱脂粉乳が余っても、バター向けの需要や在庫状況が異なるため、需給のアンバランスが生まれることがあります。
消費者にできることはありますか?
家庭での牛乳・乳製品の利用を増やすことが直接的な支援になります。レシピの共有や地域での消費促進イベントも効果的です。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
この記事はJミルクの2025年度需給見通しに基づく見解を現場の視点で整理したものです。数値・見通しは変動する可能性があります。最新の公式資料や公表データを合わせてご確認ください。