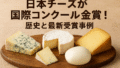蹄底潰瘍(ていていかいよう)は、乳牛の健康と酪農経営に深刻な影響を及ぼす代表的な蹄病です。発症すると歩行困難や乳量減少を招き、1頭あたり年間数万円の損失となることもあります。本記事では、蹄底潰瘍の原因、症状、予防策、治療法を最新データと実例を2級認定牛削蹄師である筆者が詳しく解説します。

歩き方がおかしい?乳牛の蹄底潰瘍に注意!
蹄底潰瘍とは?症状と経営への影響
蹄底潰瘍は、蹄底(牛の足裏部分)の角質層が損傷し、真皮が露出することで発生します。特に後肢の外側蹄に多く見られ、強い痛みを伴います。
主な症状
- 跛行(足を引きずる歩き方)
- 蹄の変形
- 食欲低下
- 乳量の減少
放置すると慢性化し、蹄葉炎(ていようえん)や白帯病(はくたいびょう)などの合併症を引き起こす可能性があります。
経営への影響
- 乳量が10〜20%減少
- 治療費の増加
- 廃用牛の増加による損失
英国の調査では、100頭規模の酪農場で蹄底潰瘍による年間損失は約2000ポンド(約30万円)に達することが報告されています。日本国内でも北海道や九州の酪農場で同様の傾向が見られます。

食欲が落ち、乳量も10〜20%減少することも

蹄底潰瘍の主な原因
蹄底潰瘍の発生には、環境、栄養、管理など複数の要因が関わります。
1. 牛舎環境の悪化
- 粗いコンクリート床や糞尿の蓄積が蹄を傷つける
- 長時間立ち続けることで蹄内部の圧力が増加
2. 栄養不良と蹄葉炎
- 高濃度飼料の過剰給与によるルーメンアシドーシス
- 分娩前後の循環障害で蹄の角質が弱化
3. 削蹄の不備
- 削蹄を怠ることで蹄のバランスが崩れ、負荷集中
- 暑熱ストレスによる蹄葉炎の悪化
4. 感染症の併発
- 趾皮膚炎(DD)が蹄を弱らせる
- 湿度の高い牛舎で発生リスク増大

分娩前後の循環障害で角質が弱化、潰瘍につながる
蹄底潰瘍の予防策
予防は治療よりも効果的で、経営損失の回避につながります。
定期的な削蹄
- 年2〜3回の機能的削蹄で蹄のバランスを維持
- 分娩前後の牛を重点的にチェック
牛舎環境の改善
- 柔らかい敷料(ストロー・ゴムマット)を使用
- 牛舎を清潔に保ち、休憩スペースを確保
栄養管理
- 粗飼料中心でルーメンアシドーシスを防止
- 分娩期にはビタミンE・セレンを補給
蹄浴(フットバス)の活用
- 週1〜2回、硫酸銅や石灰乳、ホルマリンで感染予防
早期発見
- 毎日の歩様観察で異常を見逃さない

蹄浴(フットバス)で感染症リスクを下げよう
蹄底潰瘍の治療法
早期治療が回復率を高めます。獣医と削蹄師の連携が重要です。
- 診断
蹄テスターで痛みを確認し、必要に応じてX線検査。 - 削蹄と免重
損傷部を削除し、健側の蹄にブロックを装着して負荷を分散。 - 薬剤投与
抗生物質や消炎鎮痛剤を使用。重症例では静脈注射も。 - フォローアップ
2〜4週間後に再検査し、フリーバーン牛舎で安静を確保。
日本の酪農現場では、適切な治療で80%以上が回復可能とされています。

早期発見・早期治療が回復のカギ!

経営改善と今後の展望
- 削蹄支援などの補助金活用
- 歩様監視用IoTデバイスの導入
- 酪農家同士の情報共有による技術向上
予防型管理を徹底すれば、蹄底潰瘍の発生率を半減させることも可能です。

削蹄支援や補助金で現場コストを軽減!
まとめ
蹄底潰瘍は、環境、栄養、管理の改善によって十分に防げる疾患です。定期的な削蹄と快適な牛舎環境、適切な栄養管理、そして早期発見を徹底することで、乳牛の健康と酪農経営の安定を守ることができます。

蹄底潰瘍は予防がカギ!環境・栄養・管理を見直そう
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。