蹄球びらんは乳牛の後肢に多く見られる肢蹄トラブルの一つ。放置すると跛行や乳量低下、最悪は廃用につながります。本記事は現場で「すぐに使える」実践策を中心に、原因・早期発見ポイント・治療手順・経営的な予防対策までをわかりやすくまとめました。この記事では、2級認定牛削蹄師である筆者が現場で使える実践的な対策を詳しく解説します。

蹄球びらんは後肢トラブルの代表格、放置は乳量低下に直結!
■ 蹄球びらん(ていきゅうびらん)とは
蹄球びらん(別名:蹄球糜爛、スラリーヒール)は、蹄のかかと側(蹄球部)の角質が湿潤や細菌により壊され、溝やくぼみができる病変です。多くの場合は後肢内蹄に発生し、牛舎の高湿・スラリー滞留・削蹄不足などが誘因となります。

蹄球びらんは蹄のかかと側で角質が壊れる病変

■ 主な原因(複合要因で発生)
- 牛舎の湿潤化(糞尿滞留、床面の水はけ不良)
- 削蹄不足による蹄形不良(かかとへの体重偏重)
- 細菌感染(例:Fusobacterium系など、湿潤環境で増殖)
- 過密飼育や放牧不足による立ち時間・摩耗パターンの偏り

牛舎の湿潤化や糞尿滞留が蹄球びらんを誘発
■ 早期発見のポイント(現場チェックリスト)
観察チェック(週1回の目視で)
- 蹄底・蹄球部に黒っぽい変色や溝はないか
- 蹄球に弾力がなく、押すとへこむ感触がないか
- 歩様に左右差はないか(後肢をかばう様子)
- 悪臭や腫脹、趾間の膿がないか

早期発見で跛行や乳量低下を防ぐ
■ 治療(現場でできる一次対応)
重症化を避けるため、発見したら速やかに処置します。以下は現場での一次対応例です。
- 清潔保持:患部の泥や糞を流水で洗浄し、乾燥させる。
- 損傷角質の除去:括削刀やナイフで壊死角質を慎重に除去(出血がある場合は止血を優先)。
- 消毒と保護:消毒(ヨードやクロルヘキシジン系)後、抗菌軟膏を塗布して包帯で保護。
- 蹄浴の併用:硫酸銅や亜塩素酸塩を用いた蹄浴で再感染予防。
- 獣医師連携:膿瘍形成や全身性の徴候(発熱、食欲低下)があれば獣医師に報告して適切な抗生物質治療を受ける。
実践ポイント:除去は「過不足なく」行うこと。角質を取りすぎると蹄の保護機能を損なうため、削蹄師や獣医師の判断が重要です。

患部は流水で洗浄して清潔に、乾燥も大切
■ 発生を抑える予防策(経営視点も含めて)
蹄球びらんは環境管理と作業ルーチンで大幅に発生率を下げられます。優先順位の高い対策は以下の通りです。
| 対策 | 具体例 |
|---|---|
| 定期削蹄 | 分娩前後や2〜3ヶ月毎のチェックで蹄形を整える |
| 床面管理 | スラリー排水の改善、乾燥敷料(おが屑、稲わら)を活用 |
| 蹄浴(フットバス)の運用 | 週1回〜2回(湿潤期は頻度増)、濃度・交換管理を徹底 |
| 放牧・運動 | 放牧やウォーキングで蹄の自然摩耗と血行を促進 |
| 労務管理 | 削蹄記録、歩様監視、早期発見のための担当者割当 |

蹄浴は週1〜2回、湿潤期は頻度アップで再感染防止
■ 現場事例:削蹄+蹄浴導入で発生率が低下した例
北海道のフリーストール牛舎Aでは、年2回の定期削蹄と週1回の硫酸銅蹄浴を半年間徹底した結果、蹄球関連の通報件数が導入前の約半分に減少しました。ポイントは「継続」と「データ記録」。発生履歴を残すことで対策効果が見える化され、現場のモチベーション向上にもつながります。

継続した管理が蹄球びらん予防の鍵
■ 現場ですぐ使える「応急チェックリスト」
- 牛を捕まえて後肢を観察:蹄底と蹄球を拭いて確認
- 変色・溝があれば写真を撮って記録(カメラ+牛ID)
- 軽度なら清洗→消毒→軟膏→包帯でまず保護
- 跛行が強ければ獣医師に相談し、抗生物質等の判断を仰ぐ

後肢を捕まえて蹄底・蹄球をしっかり観察!
■ Q&A(よくある質問)
Q:蹄浴はどの濃度で行えば良いですか? A:製品と推奨仕様に従ってください。濃度管理と溶液交換が重要です。獣医や薬剤メーカーの指示に従い、牛への刺激や環境負荷に配慮してください。
Q:自分で削蹄しても良いですか? A:軽度の観察は可能ですが、角質除去は技術が要ります。削蹄師や獣医の指導のもとで行うことを推奨します。
記事のまとめ
- 蹄球びらんは湿潤環境・削蹄不足・細菌感染が主因で、特に後肢内蹄に発生しやすい。
- 週1回の目視チェック(蹄球の変色・溝・弾力低下・悪臭)で早期発見が可能。
- 現場での一次対応は「清洗 → 損傷角質の除去(過度は不可) → 消毒・軟膏塗布 → 包帯保護」。重症例は獣医師と連携。
- 予防の基本は定期削蹄、床面の乾燥保持、蹄浴の継続、放牧や柔らか床材の導入。
- データ記録(削蹄履歴・発生写真・歩様観察)で対策効果を見える化し、経営的損失を抑える。

蹄球びらんは後肢内蹄に多く、湿潤や削蹄不足が主因
※ 酪農現場の実践経験に基づく解説です。現場での処置は状況に応じて獣医師と相談してください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

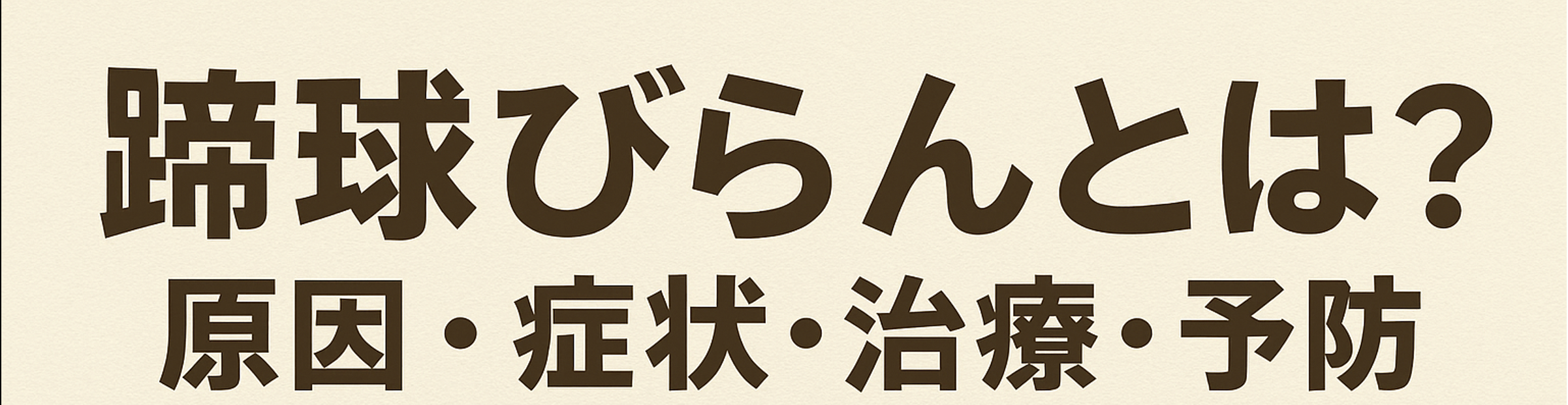

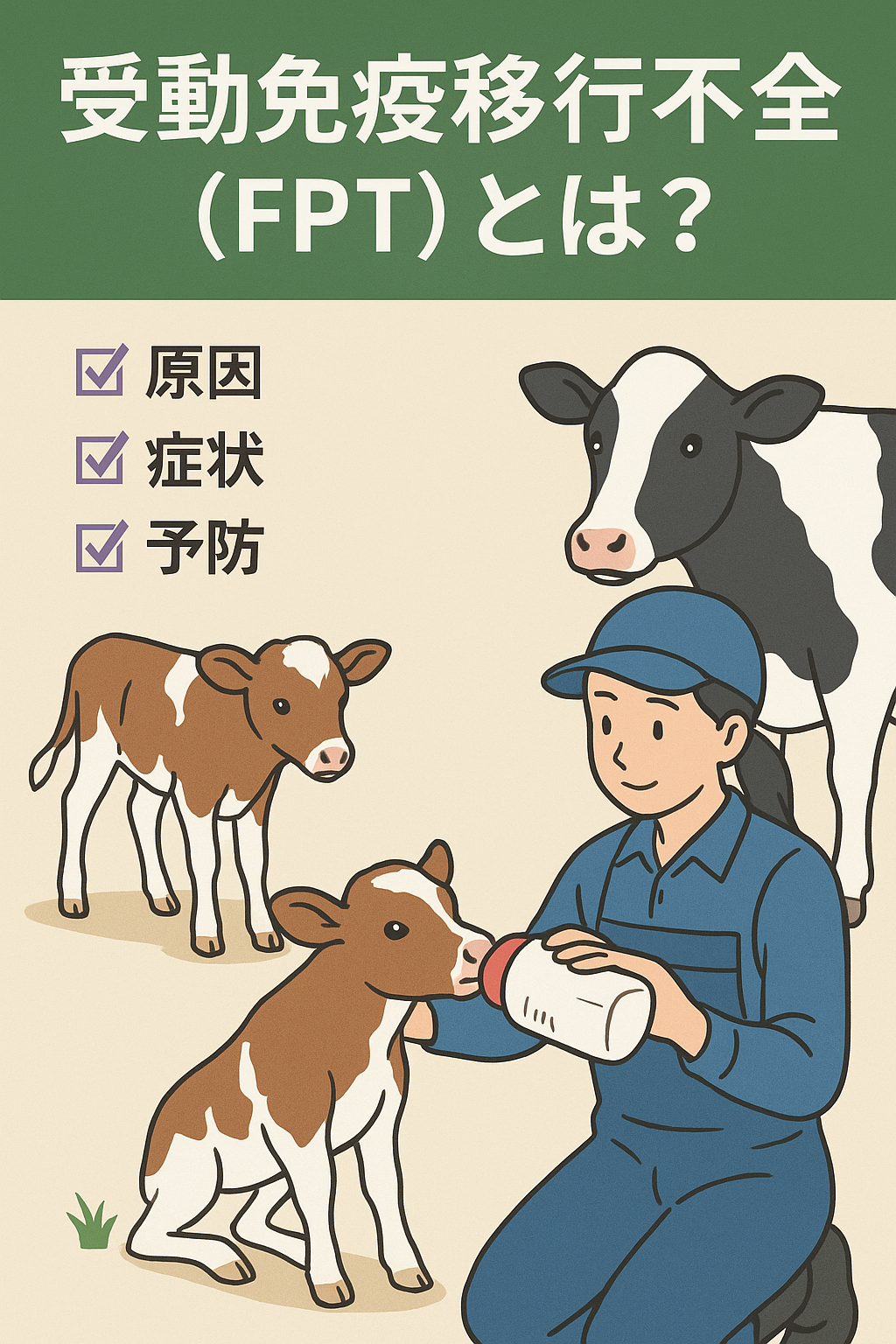
コメント