乳牛の低カルシウム血症(乳熱)は、分娩後に急激に乳汁を生成することで血中カルシウムが不足し、筋肉の弛緩や起立不能を引き起こす深刻な疾病です。本記事では、すぐに実践できるよう、乳熱のメカニズムや症状の見分け方から、乾乳期の飼料設計(DCAD調整)、陰イオン塩の効果的な使い方、マグネシウム補給のポイントまでをわかりやすく解説します。さらに、分娩後の早期発見・早期治療法や実際の牧場での成功事例も紹介。この記事を読めば、乳熱リスクを大幅に減らし、安定した乳量と健康管理を実現するノウハウが身につきます。

これ1記事で、乳熱の原因・予防・治療までまるっと理解!
1. 乳牛の低カルシウム血症(乳熱)とは?
乳熱とは、分娩後に急激に増える乳汁生成に対応しきれず、血液中のカルシウム(Ca)が不足してしまうことで発症する状態です。正式には「低カルシウム血症(hypocalcemia)」と呼ばれますが、酪農現場では「乳熱」という俗称で知られています。
- 発生タイミング:ほとんどが分娩直後(分娩前後すぐ)の48時間以内に起こります。
- 血清Ca濃度の目安:血清カルシウム濃度が7.4 mg/dL以下になると、筋肉や神経が正常に働かなくなり、典型的な乳熱症状が現れます。
- 潜在性低カルシウム血症:血清Caが8.5 mg/dL未満であっても、症状がはっきり出ない状態。見た目には元気そうでも、実はリスクが高いケースもあります。

乳熱=低カルシウム血症!分娩直後48時間が勝負!
なぜ「低カルシウム」になるの?
- 乳汁中へのカルシウム移行
分娩後、乳腺は一気に大量の乳汁を作り始めます。乳汁1リットルあたりに含まれるカルシウム量は約1.2~1.3 gといわれ、ホルスタインなど高乳量牛の場合、1日に50~60リットルの乳を搾ると、一日に60~70 gものカルシウムが乳に移行します。 - 骨からのカルシウム動員の限界
通常、牛は骨をリモデリング(壊して再生する)ことで血中カルシウムを一定に保っていますが、分娩直後の急激な需要増には追いつかず、骨からカルシウムを放出するスピードが間に合わなくなるため、血中のカルシウムが急速に不足してしまいます。

分娩直後のカルシウム需要、牛の体が追いつけないんです!
2. 乳熱の主な原因とリスク要因
2-1. 乾乳期の飼料バランスの問題
- カルシウム・カリウムの過剰摂取
乾乳期(分娩の約60日前から分娩直前までの期間)に、飼料中にカルシウムやカリウム(K⁺)が多すぎると、分娩後に必要なタイミングで骨からカルシウムを放出する副甲状腺ホルモン(PTH)の働きが鈍ります。結果として「骨からのカルシウム動員能力」が落ち、分娩直後に血中Caが急激に低下するリスクが高まります。 - DCAD(Dietary Cation-Anion Difference)の偏り
DCADとは「陽イオン(カチオン:Na⁺, K⁺)─陰イオン(アニオン:Cl⁻, S²⁻)」の差をmEq/kgで示したものです。乾乳期の飼料中のDCADが高すぎる(陽イオン過多/アルカリ性に寄りやすい)と、副甲状腺ホルモンの働きが弱まり、骨からのカルシウム動員が不十分になります。- 目標:乾乳期の飼料DCADを+200 mEq/kg以下、理想的には0~+100 mEq/kg程度に抑える
- K含量は2%以下にコントロールすることで、DCADを自然と低く維持しやすくなる

乾乳期のカルシウム過多が、むしろ乳熱の原因になるなんて!
2-2. 牛の個体特性・管理環境
- 高乳量牛種
ホルスタインのように乳量が多い品種は、分娩直後に必要なカルシウム量が多く、骨からの動員スピードが追いつかず、乳熱になる確率が高くなります。 - ストレスや環境変化
分娩前後の環境ストレス(間引き、移動、過密飼育など)はホルモンバランスを乱し、カルシウム動員機構に影響を与えることがあります。

分娩ストレスがホルモンに影響⁉ Ca動員力が下がることも
3. 乳熱の症状と発見のポイント
3-1. 臨床的低カルシウム血症の症状
- 筋肉の弛緩
起立筋(前肢・後肢)が弛緩し、立ち上がれなくなる。いわゆる「ダウナー牛」。 - 循環障害
心拍数低下、体温低下、チアノーゼ(口唇や乳頭が紫色になる)など。 - 神経症状(テタニー)
痙攣、けいれん、舌のもつれ、意識混濁。 - 食欲不振・脱力
筋力が落ち、舌を出してヨダレを流したまま動かなくなるケースもある。

立てない牛は“乳熱”を疑え!起立不能は要注意サイン
(表1)乳熱の代表的な臨床症状と重症度の目安
| 症状項目 | 軽症 | 中等症 | 重症 |
|---|---|---|---|
| 筋肉の状態 | よろめき・歩行が鈍い | 前肢が震える・後肢が広がり始める | 完全に立てない・前肢を投げ出す |
| 循環・呼吸 | 心拍・呼吸に異常はないまたはわずか | 心拍数や呼吸数が低下 | チアノーゼ、ショック兆候 |
| 神経症状(テタニー) | 痙攣は見られない | 舌のもつれや足が震えるなど軽度の痙攣 | 強い痙攣・意識障害 |
| 食欲・行動 | 食欲はあるが動きが鈍い | 食欲が減退し、ふらつきが顕著 | 食欲皆無・横臥し続ける |
3-2. 潜在性低カルシウム血症の見逃しリスク
血液検査をしないと発見が難しいため、「見た目は元気だけど血清Caは低い」ケースが意外に多くあります。潜在性低カルシウム血症を放置すると、以下のように二次的な疾病リスクが上がります。
- 乳房炎の発症率上昇
- ケトーシス(脂肪肝)などの代謝性疾患
- 第四胃の転位・捻転リスク増加
分娩後24~48時間は、血清総カルシウム濃度が8.5 mg/dL以下かどうかを検査し、潜在性乳熱の兆候を早期に発見するとよいでしょう。

見た目は元気でも“潜在性乳熱”のリスクあり!
4. 乳熱の経済的影響
- 治療コストの増加
- 獣医師呼び出し費用、カルシウム製剤や補液、点滴器具などの実費
- 重症例ではICUのような環境確保が必要になる場合もある
- 乳量の低下
- 発症から回復までの期間、通常よりも20~30%程度乳量が下がることがある
- 乳熱を繰り返すと、分娩後数週間の乳量全体が低迷し、年間通算乳量にも大きく影響
- 繁殖成績の悪化
- 初回受精率の低下
- 分娩間隔の延長(再配合理由が乳量低下や代謝性疾患による不受胎など)
- 二次疾患の発生
- 潜在性低カルシウム血症を放置すると、乳房炎・ケトーシス・第四胃変位などの発症リスクが増加し、トータルの損失がさらに拡大する
酪農試験場のデータによると、乳熱1頭当たりの直接的および間接的損失を合計すると、1頭あたり1回の発症で数十万円に上るケースも少なくありません。とくに経年繁殖成績が悪化すると、肉用牛への転換や淘汰決定にもつながるため、乳熱予防が経営安定のカギとなります。

乳熱1回で数十万円の損失⁉ 放置は経営リスクに直結!
5. 乳熱の予防・対策方法
乳熱は「一度発症すると治療が大変」なだけでなく、発症を繰り返すと牛自身の健康寿命を縮めるリスクがあります。以下の対策を組み合わせることで、発症率を大幅に低減できます。
5-1. 乾乳期の飼料管理(DCADの調整)
DCADとは何か?
- 「D(Dietary)C(Cation)A(Anion)D(Difference)」の略で、飼料中の陽イオン(Na⁺+K⁺)―陰イオン(Cl⁻+S²⁻)の総計差を示します。
- 飼料成分表から各イオンの含量をmEq/kgに換算して、以下の式で算出します。bashコピーする編集する
DCAD(mEq/kg乾物)=[Na⁺(mEq/kg)]+[K⁺(mEq/kg)]−[Cl⁻(mEq/kg)]−[S²⁻(mEq/kg)] - 数値が高いほど血液はアルカリ性に傾き、副甲状腺ホルモン(PTH)の働きが鈍ってカルシウム動員が低下。
- 乾乳期の目標値は「+200 mEq/kg乾物以下」、理想は「0~+100 mEq/kg程度」。

DCADが高すぎると“乳熱リスク”が急上昇!
DCADを低く保つ具体的手法
- 飼料配合の見直し
- 乾乳期の配合飼料に含まれるカリウム(K⁺)が2%以上だとDCADが上昇しやすくなるため、K含量を2%以下に抑える配合を検討する。
- 原料飼料(例:牧草やデントコーン)だけで高Kになってしまう場合、K吸着剤(ベントナイトなど)や低K飼料への切り替えを検討。
- 陰イオン塩の添加
- 適切な陰イオン塩(塩化アンモニウムや硫酸アンモニウムなど)を混ぜて、DCADをわざと低く維持。
- 他のミネラルバランスを崩さないよう、配合設計は専門家と相談のうえ行う。
- 尿pHモニタリング
- 乾乳期の尿pHを6.0~6.5に維持できていれば、DCADが適切に管理できている証拠。
- 簡易pHペーパーで、1~2週おきにチェックすると管理しやすい。

陰イオン塩の追加でDCADをコントロール!
牧場での実践例
- 乾乳期開始から分娩直前までの60日間、配合飼料と自給飼料の混合比を見直し、DCADを「+150 mEq/kg前後」に調整。
- その結果、分娩後に起立不能牛(ダウナー牛)が前年の3%から0.8%に低減。
5-2. 陰イオン塩の活用(4.5%添加が目安)
乾乳期飼料に陰イオン塩を適正量添加すると、DCADを下げるだけでなく、尿pHを低下させることで体内を弱い酸性に保ち、副甲状腺ホルモン(PTH)の分泌を促進し、骨からのカルシウム動員をサポートします。
- 推奨添加量:飼料乾物重量比でおよそ4.5%
- 4.5%添加により、尿pHが6.0~6.5程度まで下がり、乳熱発生率が顕著に低下したという報告多数(北海道立畜産試験場)。
- 6%まで増やすとさらにDCADは低くできるものの、食いつき不良や乳量低下が起こりやすくなるため、4.5%が実用的。
- 添加時の注意点:
- 塩味による食欲低下防止:陰イオン塩は苦味や塩味が強く、乾乳期牛は食いつきが落ちる可能性があるため、好塩性飼料(ビートパルプやナチュラルソルト入り粗飼料など)を一定量混ぜる工夫をする。
- ミネラルバランスの偏りに注意:陰イオン塩を入れると、他の微量ミネラル(Mg、Pなど)のバランスにも影響が出やすくなるため、配合設計は専門家と綿密に相談して行う。

尿pHが“6.0〜6.5”ならカルシウム動員◎
研究報告のサマリー
- 添加量3%:尿pHにほとんど変化なし、血中Caにも影響なし
- 添加量4.5%:尿pHが6.0~6.5に低下、骨からのCa動員促進 → 乳熱発生率が50%以上減少
- 添加量6%:尿pHはさらに低下するが、飼料摂取量・乳量が低下し、実用性に課題あり(北海道立畜産試験場研究報告)
5-3. マグネシウム(Mg)の適正補給
マグネシウムは、カルシウム代謝において重要な役割を持ちます。特に乾乳期にMgが不足すると、副甲状腺ホルモン(PTH)受容体の感受性が低下し、骨からのカルシウム動員効率が落ちてしまいます。
- 推奨Mg含有量:乾乳期の総飼料中マグネシウム濃度を0.4~0.5%程度に保持する
- 吸収促進策としてのDFA III(オリゴ糖):
- J-STAGE論文によれば、DFA IIIは小腸のタイトジャンクションを緩め、Mg(およびCa)の吸収を高める作用があると報告されています。
- 乾乳期の飼料にDFA III含有飼料を一定割合(例:乾物10~20g/牛・日)併用すると、腸管からのMg吸収率が上がり、結果的に骨からのCa動員をサポートします。
- 過剰Mgのリスク:Mgを過剰に含ませると、腸管でのカルシウムの吸収を阻害してしまうため、指示された推奨量を守ることが重要です。

Mg不足=Ca動員ダウン!乳熱の隠れ原因に
5-4. 分娩後のカルシウム製剤による予防投与
分娩直後にカルシウム製剤(例:グルコン酸カルシウムや酢酸カルシウム)を経口または静脈投与して、血中Caを一時的に上昇させる方法もあります。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 投与前に血清Caを確認する
- 分娩後24時間以内に血清総Ca検査を行い、8.5 mg/dL未満なら潜在性低カルシウム血症の可能性あり。
- 血清Caが正常範囲(8.5~10.5 mg/dL)なのに安易に投与すると、高カルシウム血症を招く恐れがあります。
- 投与方法
- 静脈投与:グルコン酸カルシウム300~500 mLをゆっくり点滴する。心拍数や体調を観察しながら投与速度を調整。
- 経口投与:酢酸カルシウムを500 mL程度飲ませる方法。静脈投与と比べて手間は少ないが、重症例には効果が追いつかない場合あり。
- ビタミンD3筋注は現在は非推奨
- 以前はビタミンD3筋肉注射で腸管からのCa吸収を促進しようという方法がありましたが、副反応(高カルシウム血症や腎障害)リスクが指摘され、最近はあまり使われません。

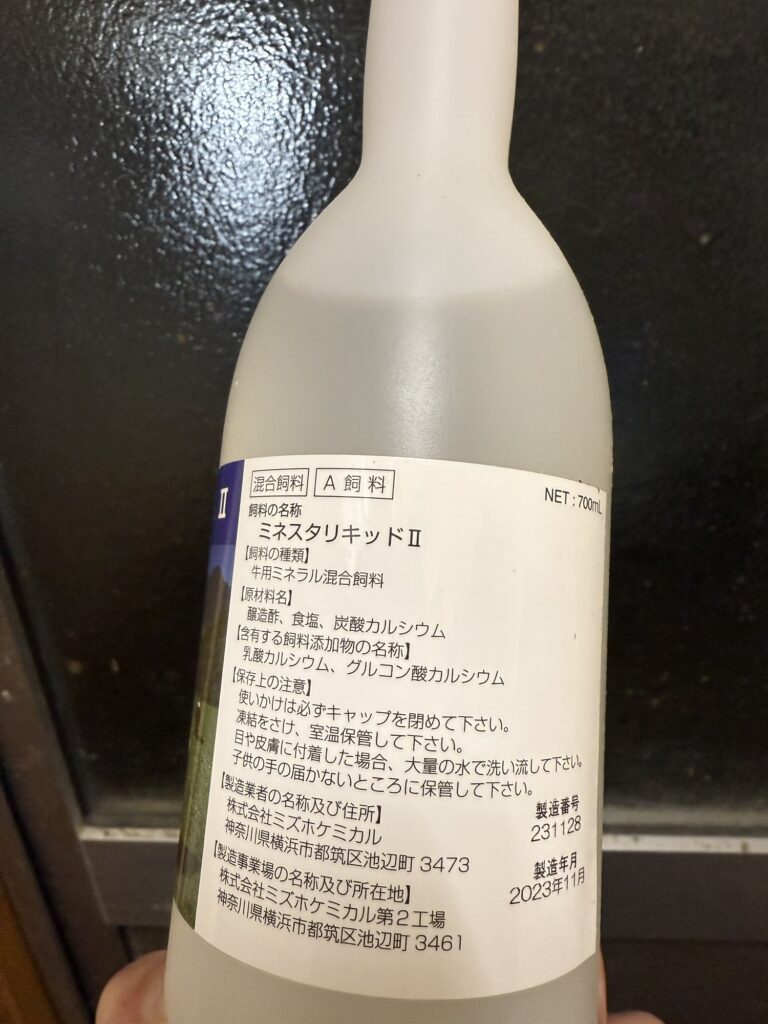

Ca投与前に“血清Caチェック”が鉄則!
NOSAI道央のガイドライン
- 分娩後48時間以内に血清Caが8.5 mg/dL未満なら、Ca製剤投与を検討する。
- 静脈投与後は経口投与で維持療法を行い、再発を防ぐ。
5-5. モニタリングと早期発見のポイント
- 血清Ca検査
- 分娩後24時間と48時間の2回、血清総カルシウムをチェック。8.5 mg/dL未満であれば、潜在性乳熱対策として経口Ca投与や食欲管理を強化。
- 尿pHの測定
- 乾乳期~分娩前に尿pHを週1~2回チェックし、6.0~6.5付近をキープ。適正なDCAD管理の指標となる。
- 行動・食欲観察
- 分娩直後は食欲が落ちるものの、完全に食べない・動けない場合は乳熱を疑い、血液検査を優先。
- 初期のふらつきや呼吸数の変化も見逃さないよう、朝夕2回は牛群を見回り、異常がないか確認する。

“フラつき+食欲↓”は、潜在性乳熱のサインかも?
6. 牧場での実践例:私の牧場の場合
当牧場では、以下のような流れで乳熱予防と早期発見に取り組んでいます。
- 乾乳期の飼料設計
- 乾乳期60日目から、配合飼料を全体の15%程度に抑え、自給粗飼料(ビートパルプ混合)を主体に配合。
- DCADを+150 mEq/kg前後に維持するため、K含有量を1.8~2.0%に抑え、陰イオン塩(塩化アンモニウム)を4.5%添加。
- マグネシウム含有量は0.45%に設定し、DFA III含有飼料を一日あたり200 g(乾物重量ベース)併用。
- 分娩直前モニタリング
- 分娩予定が近づいた牛は、尿pHを毎週チェック。尿pHが6.5より高い牛には、追加で陰イオン塩を配合。
- 分娩予兆がある牛は頭絡で仕切り、他群と分けて特別管理。
- 分娩後の早期チェック
- 分娩後24時間以内に、簡易血清Ca検査キットでスクリーニング。8.5 mg/dL未満なら経口酢酸カルシウム500 mLを給与。
- 食欲や歩様のチェックも同時に実施し、異変があればすぐに獣医師を呼ぶ。
- 継続的フォローアップ
- 分娩後3日間は毎朝・毎夕の2回、牛群を回って姿勢・呼吸・食欲を観察。
- 血清Caが正常範囲まで回復した牛にも、分娩後5日目に再度血清Ca検査を行い、潜在性乳熱の確認を行う。
実践結果:
過去1年間で分娩後にダウナー牛が発生したのは全体の0.7%(年間約300頭中2頭)にとどまり、前年の3.5%から大幅に改善されました。乳量も分娩後1~2週間目の減少幅が小さく、繁殖成績も安定。

異常が出たら“すぐ獣医”。ためらわないのが基本!
7. まとめ:乳熱予防のポイント
- 乾乳期のDCAD管理を徹底する
- 配合飼料と自給飼料のバランスを見直し、DCADを+100~+200 mEq/kg以下に維持
- カリウム含量を2%以下に抑えつつ、陰イオン塩(4.5%)で調整
- マグネシウムを適切に補給する
- 乾乳期総飼料中のMg含有量を0.4~0.5%に設定し、DFA IIIなど吸収促進飼料を併用
- 分娩後のモニタリングを強化する
- 分娩後24~48時間に血清Ca検査を実施し、8.5 mg/dL未満なら経口Ca投与
- 分娩直前の尿pHチェックで、DCAD管理の適否を見極める
- 治療・管理プロトコルをあらかじめ確立しておく
- 静脈内Ca製剤投与の手順や経口Ca給与法、体温管理・補液方法などをマニュアル化
- 獣医師と連携し、いつでも相談できる体制を整備
- 現場データを継続的に蓄積・分析する
- 発症例、検査値、飼料設計の変更履歴を記録し、定期的に振り返って改善点を抽出する

Ca検査は“分娩後24~48h”がベストタイミング
最後に
乳牛の低カルシウム血症(乳熱)は、一度発症すると牛の健康寿命や繁殖成績、乳量に大きな影響を与えます。しかし、乾乳期からの飼料設計と分娩後の綿密なモニタリング・早期対策を行うことで、発症率を大きく抑えられることが多くの研究で示されています。特に「DCAD管理」「陰イオン塩添加」「マグネシウム補給」は基本中の基本ですので、まずはこれらをしっかりおさえて、分娩前後の環境整備に取り組んでみてください。
この記事が、これから乳牛の分娩期管理に取り組む方々や、すでに乳熱に悩んでいる酪農家のみなさまの参考になれば幸いです。

乳熱は健康寿命や繁殖成績に大ダメージ!だから予防が超大事!
【関連記事】
BHB(β-ヒドロキシ酪酸)とは?ケトーシス対策と健康維持の実践ガイド
NEFA(血中遊離脂肪酸)とは|DMI不足解消から血糖値/BHB検査まで徹底ガイド
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

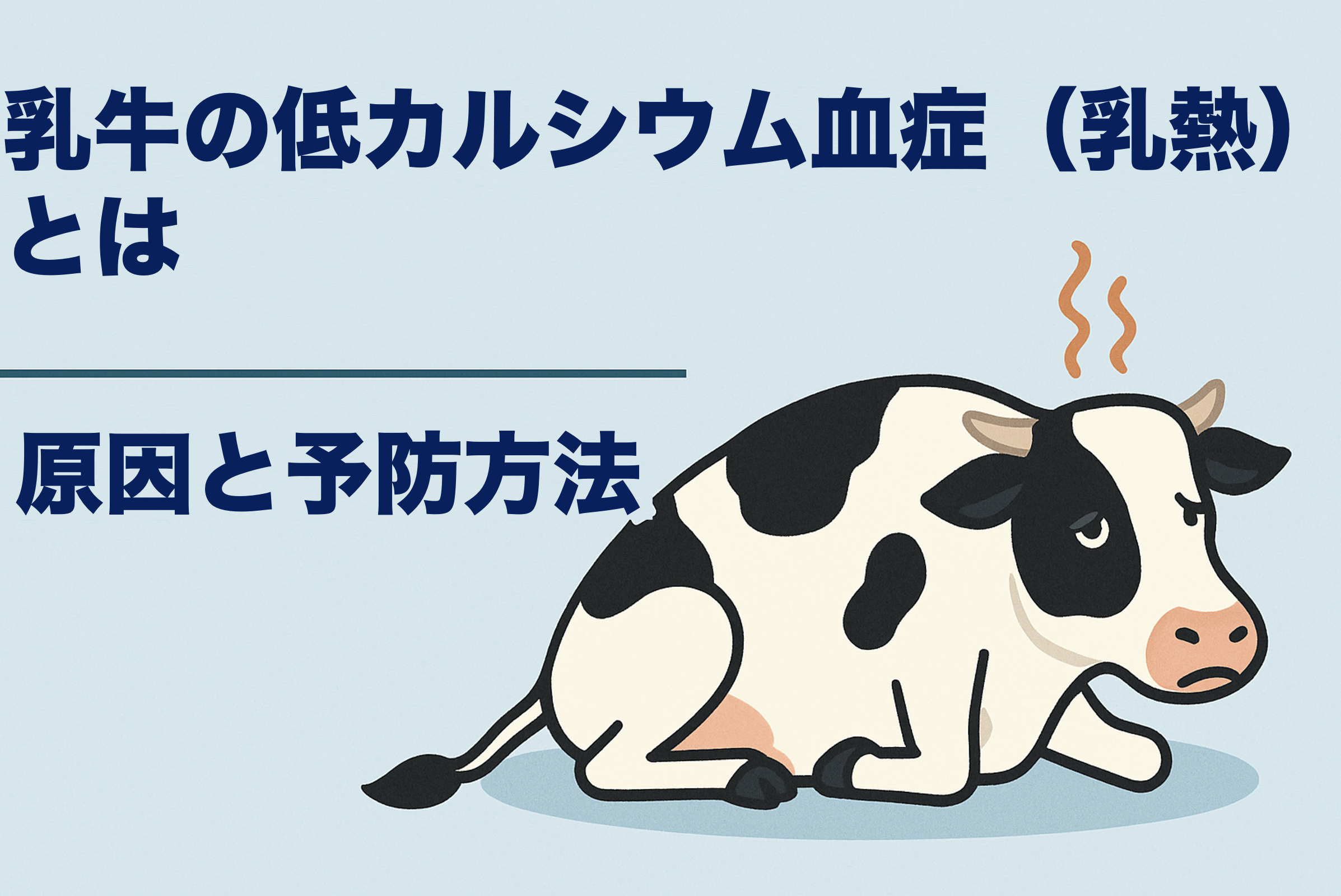



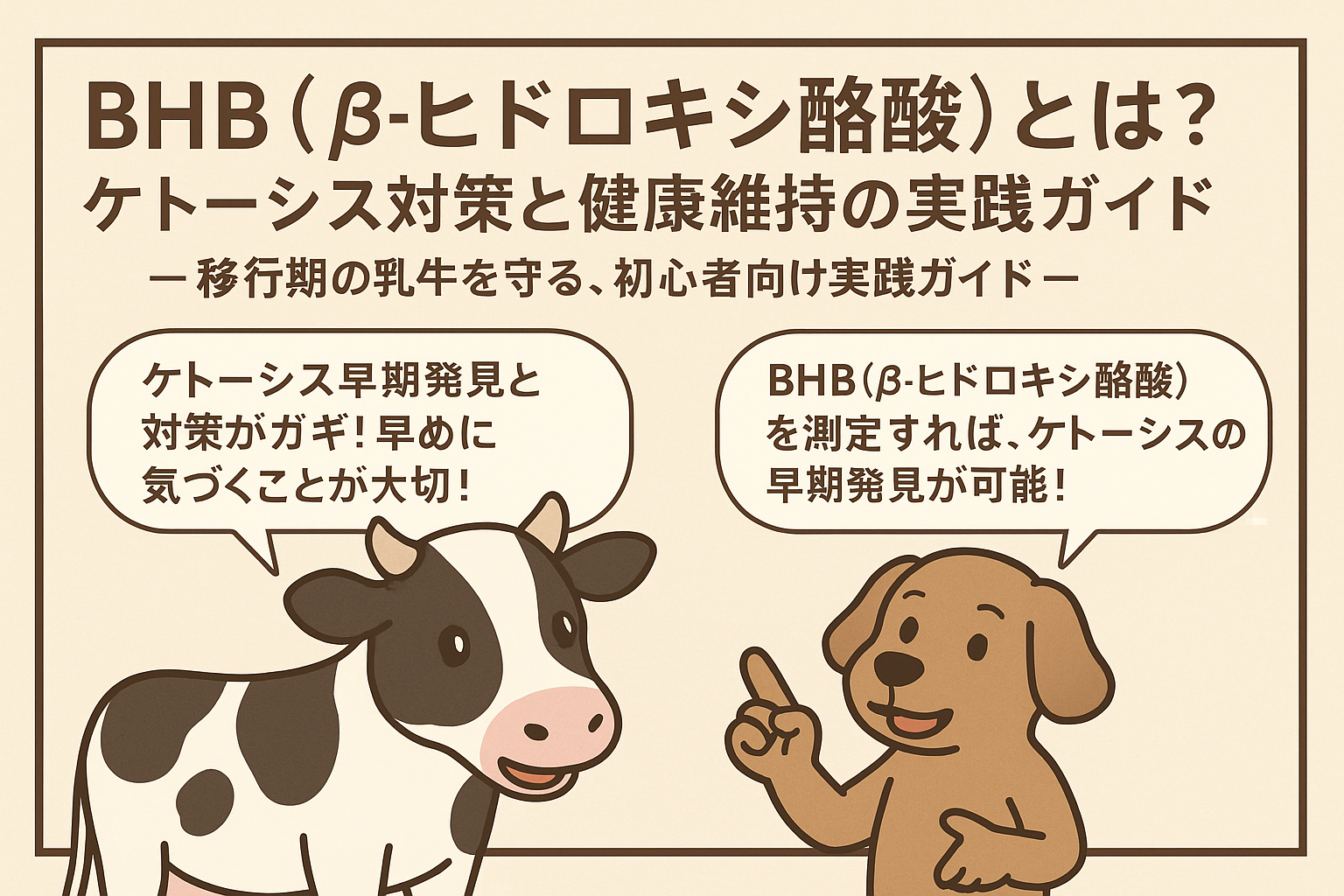
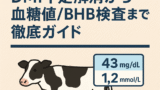
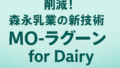

コメント